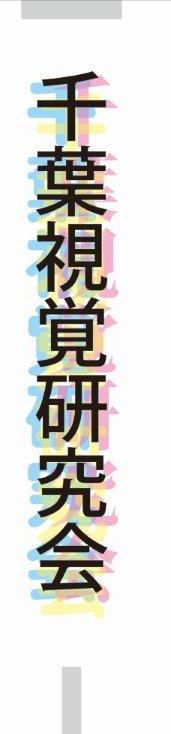
※ロゴは後藤雅宣先生作
| お知らせ |
|---|
第108回 の研究会では、千葉大学大学院 融合理工学府イメージング科学コース・博士後期課程の渡辺修平さんに 『塗装表面の質感定量化事例紹介』
というタイトルで、研究紹介をしていただく予定です。
---
<研究紹介をしてくださる方を募集中です!>
| 開催予定 |
|---|
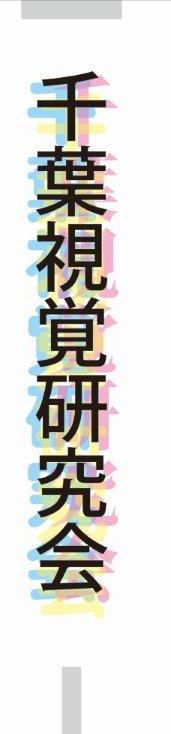
※ロゴは後藤雅宣先生作
| 活動内容 |
ほぼ月1回のペースでメンバーや招待講演者の研究紹介を行い、意見交換をしています。
| 開催記録 |
<2018年度>
第108回 :2019年 3月20日(水) 渡辺修平,塗装表面の質感定量化事例紹介
第107回 :2019年 1月 8日(火) 特別講演会,Maria Olkkonen & Toni Saarela
第106回 :2018年11月28日(水) 村田佳代子,皮膚感覚ベクションのメカニズムの検討
第105回 :2018年10月30日(火) 高橋良香,照明による環境の彩度変化への順応
第104回 :2018年 8月 4日(土) 特別企画:DIC川村記念美術館 ブリジット・ライリー展見学
第103回 :2018年 7月10日(火) 森本拓馬,Colour constancy for glossy objects under complex lighting
environment
第102回 :2018年 6月20日(水) 白木厚司,複数画像を表示可能な指向性ボリュームディスプレイの開発
第101回 :2018年 5月31日(木) 上地泰一郎,要素円が構成する領域の拡大によって要素の見えの大きさが縮小する
<2017年度>
第100回 :2018年 3月29日(木) 塩入諭,注意の無意識性
第99回 :2018年 2月21日(水) 梯絵利奈,クラスタリングに基づくアゲハチョウ科の色彩分析
第98回 :2018年 1月 5日(金) 特別企画:色覚と質感セミナー
第97回 :2017年11月30日(木) 緑川晶,認知症発症後の感覚・認知・社会的な変化
第96回 :2017年10月31日(火) 山田真希子,認知バイアスの脳内機構
第95回 :2017年 9月21日(木) 小林美沙,画像観察による感情喚起が視覚の時間精度に与える影響
第94回 :2017年 8月 3日(木) 濱田大佐,色字共感覚における共感覚色の決定過程
第93回 :2017年 7月26日(水) 大住雅之,最近の色彩・質感計測機器と測定の実際
第92回 :2017年 6月14日(水) 大倉典子,バーチャル環境と実環境を併用した、樹脂表面の質感の感性評価 樹脂表面の印象に与える質感
第91回 :2017年 4月20日(木) 小山 慎一,実験心理学的手法による医薬品・食品パッケージデザインの研究
<2016年度>
第90回 :2017年 3月22日(水) Hiroshi Ono, Revisiting Cyclops and his Eye
第89回 :2017年 3月 3日(金) Qian Qian,Cueing and sequential effects in visual spatial orienting
第88回 :2017年 2月 2日(木) 仲谷正史,音響信号を利用した触質感提示の試み
第87回 :2016年12月 7日(水) 方昱,単眼性のマイクロサッカードは存在するのか?
第86回 :2016年11月10日(木) 渡辺安里依,Peeping birds: Using observational spatial memory tasks to study avian
metacognition
第85回 :2016年10月 6日(木) 永登大和,他者の視線が観察者の注意に及ぼす影響と個人差に関する研究
第84回 :2016年 8月 3日(水) 徳永留美,目撃証言における顔色の表現と証拠能力
第83回 :2016年 6月30日(木) 向井志緒子,商品パッケージデザインにおける構成要素同士の印象評価の類似性が商品の美的印象へ与える影響
第82回 :2016年 6月 2日(木) 河村康佑,他者の痛み観察時の不快感を喚起する要因の検討
第81回 :2016年 4月27日(水) 田中緑,実物体と画像を用いた質感解析に関する研究
<2015年度>
第80回 :2016年 3月24日(木) 特別講演:Sérgio Nascimento, Seeing colors in nature ? what do we learn from spectral
imaging
第79回 :2016年 3月14日(月) 今泉修,集合体への嫌悪に関わる視覚刺激特性と性格特性
第78回 :2016年 2月22日(月) 菊地久美子,肌の明るさ知覚に影響を及ぼす色素斑の特徴理解
第77回 :2015年12月17日(木) 特別講演:Philip Grove,Single and double vision in the central binocular field
第76回 :2015年11月12日(木) 米村朋子,身体運動の随意性保持と自他弁別要因の検討
第75回 :2015年10月28日(水) Miguel Angel Martinez-Domingo,High dynamic range scientific imaging: Advantages
and limitations
第74回 :2015年 9月18日(金) 森本拓馬,オプティマルカラー仮説に基づく照明光推定
第73回 :2015年 7月 9日(木) 特別講演:Hannah Smithson, Colour in light and materials
第72回 :2015年 6月 4日(木) 宍倉正視,特色印刷インキ赤色の見えに関する評価-各色覚タイプにおける照明条件の影響-
第71回 :2015年 4月23日(木) 岡崎聡,2純音の同時性の窓~2音の周波数距離の関数として~
<2014年度>
第70回 :2015年 3月13日(金) 勝田徹,文化財写真の撮影の実際
第69回 :2015年 2月 5日(木) 奥村治彦,高臨場感ディスプレイの研究:-片目で奥行きを感じさせる単眼表示技術-
第68回 :2014年12月10日(水) 村越琢磨,変化の検出と変化の位置判断のメカニズム
第67回 :2014年11月19日(水) 中島由貴,美術館・博物館における最適な照明・色彩視環境の研究
第66回 :2014年10月29日(水) 實森正子,ハトにおける画像知覚と視覚的注意:視覚探索課題と高速逐次視覚呈示法を用いて
第65回 :2014年 9月16日(火) 小林裕幸,私たちは粒状から何を感ずるか
第64回 :2014年 7月28日(月) 大竹潤己,金属の質感空間構築のための主観評価実験方法について
第63回 :2014年 6月26日(木) 大沼一彦,眼の中の散乱光測定
第62回 :2014年 5月28日(水) 辻田匡葵,身体運動-視覚間時間再較正に寄与する処理過程の検討
第61回 :2014年 4月16日(水) 竹下友美,「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」の取り組み
<2013年度>
第60回 :2014年 3月 5日(水) 小松由梨果,ハトにおけるKanizsa型錯視 -明るさ弁別課題・プライミングを用いた検討-
第59回 :2014年 2月12日(水) 今泉修,風景や絵画が誘発する視覚的不快 – 片頭痛患者と健常群の比較
第58回 :2013年12月18日(水) 東洋邦,屋内LED照明の不快グレア評価方法究
第57回 :2013年11月20日(水) 鈴木晴翔・国分詠美子,変動照明に対する在室者の知覚に関する研究
第56回 :2013年10月23日(水) 牛谷智一,ミツバチの齢間分業と認知発達
第55回 :2013年 9月 9日(月) 大武美保子,写真を用いた会話-共想法による認知活動支援
第54回 :2013年 7月23日(火) 津村徳道,質感工学とその応用
第53回 :2013年 6月28日(金) 今井良枝,LED照明の好ましさに基づいた演色性評価
第52回 :2013年 6月 6日(木) 佐久間直人,複数同時に呈示された数字の高速処理に寄与する諸要因の検討
第51回 :2013年 4月25日(木) 黒岩眞吾,人と機械の音声言語処理
<2012年度>
第50回 :2013年 3月21日(木) 桑山哲郎,「画像技術史」の授業と錯視の関係-伝えたいことと生徒の興味との食い違い
第49回 :2013年 2月21日(木) 井上はるか,顔画像の動的特性が表情の認知過程に及ぼす影響 ―評定尺度法と心理物理学的測定法による検討―
第48回 :2012年12月20日(木) 鈴木卓治,ある2型3色覚者の単波長光の色の見え方に関する事例報告
第47回 :2012年11月28日(水) 山口秀樹,視野の色彩分布と空間の明るさ感
第46回 :2012年10月31日(水) 草野勉,観察時の頭部位置および背景の傾きによる両眼視方向の偏位
第45回 :2012年 8月27日(月) 山本昇志,光沢再現と三次元視覚
第44回 :2012年 7月26日(木) 堀内隆彦,HDR画像のトーンマッピングと評価方法
第43回 :2012年 6月27日(水) 桂重仁,木材画像の質感に影響を与える要素 ~色と空間周波数からの検討~
第42回 :2012年 5月23日(水) 和田有史,食品の質感視知覚
第41回 :2012年 4月26日(木) 戸部和希,白色LED光源の演色性と照明空間の印象の評価
<2011年度>
第40回 :2012年 3月28日(木) 後藤雅宣,構成学に関する研究紹介
第39回 :2012年 2月 9日(木) 大北碧,ハトにおけるカテゴリ探索の検討 -顔合成画像を用いて-
第38回 :2011年12月22日(木) 岩坂正和,生物磁気の最近の話題
第37回 :2011年11月24日(木) 木村敦,ブランドロゴの記憶色
第36回 :2011年10月13日(木) 兼松えりか,色になじみのある物体による色の見えへの影響
第35回 :2011年 9月26日(月) 今泉祥子,ハッシュ関数に基づくコンテンツ保護技術
第34回 :2011年 7月28日(木) 澤山正貴,輝度エッジの解釈過程における肌理とエッジの処理の相互作用 ―肌理上の水染み現象を用いた検討
第33回 :2011年 6月23日(木) 矢田紀子,色覚特性のニューラルネットワークモデル
第32回 :2011年 6月 2日(木) 高橋良香,視物質メラノプシンを含む網膜神経節細胞が関与する非視覚的作用メカニズムの推定
第31回 :2011年 4月 7日(木) 眞鍋佳嗣,Virtual or Real ? 複合現実感技術
<2010年度>
第30回 :2011年 3月 3日(木) 相田紗織,両眼視差に基づく見かけの奥行き:逆二乗法則からの逸脱
第29回 :2011年 2月10日(木) 喜多靖,HIDと白色LEDにおける光源色の見えと測色値の不一致
第28回 :2010年12月 9日(木) 谷口昌志,記憶質感と好ましい粒状性について -ノイズのタイプを考慮して-
第27回 :2010年11月 4日(木) 川本一彦,粒子フィルタに基づく動画像解析
第26回 :2010年10月14日(木) 吉澤陽介,色空間における慣用色名認識の定量化の試み ~JIS Z 8102「物体色の色名」における慣用色名について~
第25回 :2010年 9月 9日(木) 一川誠,両眼視差量が画像の印象におよぼす効果>
第24回 :2010年 8月 5日(木) 小山慎一,視覚の臨床神経心理学:患者から学ぶ視覚の仕組み
第23回 :2010年 7月 1日(木) 平井経太,空間速度コントラスト感度関数の測定・モデル化と動画像評価への応用
第22回 :2010年 5月19日(水) 池田光男,空間認識、そして色の見え
第22回 :2010年 5月19日(水) Janprapa Poungsuwan,写真の中にも色の恒常性 (Color constancy
demonstrated in a photograph)
第21回 :2010年 4月22日(木) 中村哲之,錯視に関する比較認知研究
<2009年度>
第20回 :2010年 3月17日(水) 大塚一路,人の集団に関する新たな評価方法の考察 ~ ファイナンス理論を用いたサービスレベルの評価方法 ~
第20回 :2010年 3月17日(水) 下村義弘,『カラダの百科事典』に見るヒトの科学的考察
第19回 :2010年 2月10日(水) 平山順,概日リズムの光入力シグナルとDNA損傷応答の類似性
第18回 :2009年12月 9日(水) 阿部悟,視野闘争の検討を通じた異眼間情報統合処理の解明
第17回 :2009年11月18日(水) 富永昌治,絵画の質感を追求するディジタルアーカイビングについて
第16回 :2009年10月28日(水) 櫻井建成,非線形振動子とそれを用いた画像処理
第15回 :2009年 9月 4日(金) 桐谷佳惠,電子辞書画面デザインと語の関連性の可視化
第14回 :2009年 7月16日(木) 勝浦哲夫,光環境とヒト ー味覚,時間感覚,生理機能に及ぼす光の影響
第13回 :2009年 6月18日(木) 吉岡陽介,歩行時の空間把握と中心視および周辺視
第12回 :2009年 5月21日(木) 吉川拓伸,肌色の白さ知覚について―色相および彩度が肌色の白さ知覚に与える影響―
第11回 :2009年 4月16日(木) 三分一史和,脳信号データの時空間解析
<2008年度>
第10回 :2009年 3月 5日(木) 青木直和,ノイズ付加による画質向上効果
第 9回 :2009年 2月12日(木) 溝上陽子,環境の色分布に影響される色知覚
第 8回 :2008年12月11日(木) 木村英司,瞳孔反応を用いた視覚研究
第 7回 :2008年11月 6日(木) 大沼一彦,眼内レンズと色収差、球面収差
第 6回 :2008年10月 9日(木) 小山慎一,幻肢とラバーハンドイリュージョンを通じて触知覚メカニズムを考える
第 5回 :2008年 9月 3日(水) 高橋良香,生体リズムとその光受容システム
第 4回 :2008年 7月30日(水) 牛谷智一,視覚的体制化の比較認知科学
第 3回 :2008年 6月18日(水) 外池光雄,視覚の脳内情報処理に関する非侵襲的計測
第 2回 :2008年 5月21日(水) 宗方淳,建築空間の見せ方、見方
第 1回 :2008年 4月23日(水) 一川誠,能動的観察によるフラッシュラグ効果の低減
<関連講演会>
2018年 3月 9日(金) International Symposium on Lighting
Environment and Visual Perception (「照明環境と視知覚に関する国際シンポジウム」)
2017年 3月17日(金) MAIS-Project シンポジウム
2014年 6月10日(火) 土谷尚嗣 (Monash University), The integrated information theory of consciousness
applied to the empirical electrophysiological recording data sets
2011年 3月 3日(木) Brian Rogers (University of Oxford), Perception, art and
illusion: Where have all the illusions gone?
2010年 4月16日(金) M. Ronnier Luo (University of Leeds), Holy Grail of Colour Appearance
Research
2009年 7月29日(水) James A. Ferwerda (Rochester Institute of Technology), Envisioning the
material world
| 開催日 | 概要 | |
|---|---|---|
| 第107回 | 2019/1/8 (火) |
Dr. Maria Olkkonen (Dept. of Psychology, Durham Univ.)と、Dr. Toni Saarela (Dept. of Psychology, Univ. of Helsinki)Maria () |
| 特別講演会 | ||
|
The role of prior knowledge in color perception |
||
| 第106回 | 2018/11/28 (火) |
村田 佳代子 (千葉大学大学院 人文科学研究院) |
| 皮膚感覚ベクションのメカニズムの検討 | ||
|
止まっている電車に乗っている時に、隣のホームに停車している電車が走り出したところを見ると、あたかも自分の乗っている電車が動き出したかのように感じることがある。こうした現象を視覚誘導性自己運動知覚(ベクション)と呼ぶ。我々は外界を移動するときに、動き始めた方向の情報を前庭系から受け取り、その後、視覚系からは移動中に生じる光学的流動(オプテカルフロー)を移動方向情報として受け取る。また、こうした流動情報は聴覚では音が、皮膚感覚では空気が同様の情報として受け取ることが知られている。しかしながら、皮膚感覚から受け取る情報がどのように移動情報として成立するのかというメカニズムについて解明はされていない。そこで、皮膚感覚から受け取る情報が移動情報となる特徴について前庭系刺激と視覚系刺激を用いて検討を行った。その結果、皮膚感覚単体では移動情報として成立しないこと、前庭系との相互作用が認められること、飽和速度の存在、変化を伴う皮膚刺激は前庭刺激と同等の早さで移動情報を受け取れることが確認された。更に、視覚系との関係を検討すると皮膚感覚に与えられる温度の違いが視覚刺激で生じるベクションにも影響を与えることが確認された。前庭系と視覚系の刺激を同時に呈示した場合と前庭系と皮膚感覚系に同時に刺激を定時した場合では、後者の方が早くベクションを知覚することが確認された。これらの結果から得られた、皮膚感覚からの移動情報の成立メカニズムを報告する。。 |
||
| 第105回 | 2018/10/30 (水) |
高橋 良香 (千葉大学大学院 工学研究院) |
| 照明による環境の彩度変化への順応 | ||
|
ヒトには照明光の分光分布の違いによって物体の色の見え方が大きく変化しないという、色恒常性が備わっている。色恒常性には、照明光の色相変化に対する順応が関わっていると考えられ、多く検討されている。しかし、照明光による彩度変化についてはほとんど検討されていない。色コントラストに対する順応や画像の彩度に対する順応効果が報告されているが、いずれもディスプレイ上の刺激を用いた研究である。そこで、本研究では、照明による環境の彩度変化がもたらす色知覚への影響について検討する。
照明の色温度(白色を照らした時の色)は同じだが、赤緑の方向の色域(彩度)が大きく変化する2つの光源(高彩度光照明、黒体類似照明)を用いて、色の見えに関する実験を行った。実験1では「高彩度光照明に十分順応した時」「その後、黒体類似照明に変化した直後」「黒体類似照明に十分順応した時」において色票および実物体の色の見えをエレメンタルカラーネーミング法で応答させた。被験者の彩度知覚は、黒体類似照明に変化した直後に大きく低下し、黒体類似照明に十分順応した時、回復することが予想された。実験の結果、色の見えの変化は、緑色相では確認されなかったが、赤色相では予測通りとなった。実験2では、実験1で用いた2つの照明光のいずれかに順応した後、指定の物体に注目し、2つの照明光の混合比率を調節した10種類の照明光のうち、どの照明光での色の見えが自然かを応答させた。実験の結果、順応した照明光に近い照明光の時に自然な色の見えと判断された。
以上より、実環境における照明による物体の彩度変化に対しても、彩度順応効果が生じることが示された。
|
||
| 第104回 | 2018/8/4 (土) |
特別企画:美術館見学 |
| DIC川村記念美術館 ブリジット・ライリー展見学 | ||
|
DIC川村記念美術館で、2018年4月14日(土)-8月26日(日)に開催されていた特別展「ゆらぎ ブリジット・ライリーの絵画」を鑑賞します。 |
||
| 第103回 | 2018/7/10 (火) |
森本 拓馬 (Department of Psychology, University of Oxford) |
| Colour constancy for glossy objects under complex lighting environment | ||
|
For glossy objects, the light reflected from the surface is a weighted sum of two types of reflection: a
diffuse reflection in which the illuminant spectrum is modified by the surface reflectance, and a specular
reflection in which the scene illuminant is returned spectrally unmodified. I will present three experiments
that investigate mechanisms to support colour constancy for such objects. First, we conducted an experiment
to judge surface and illuminant colour changes under point light sources. Second and third experiments,
however, explored our ability to identify surface colours of glossy objects under environmental illumination
that introduces a complex spatial pattern of specular highlight on the surfaces. All experiments employed
computer-rendered objects that take account of the complex interaction between material and illumination.
Specular reflection showed its potential to aid colour constancy, but the effect strongly depended on the
type of task and tested conditions. |
||
| 第102回 | 2018/6/20 (水) |
白木 厚司 (千葉大学 統合情報センター) |
| 複数画像を表示可能な指向性ボリュームディスプレイの開発 | ||
|
映像システムそのものが3次元であるボリュームディスプレイは,特殊なメガネ等を必要とせず,3次元像をそのまま表示できる究極の3次元表示技術の一つである.我々の研究グループではボリュームディスプレイが奥行き方向にも情報を持つという特徴に着目し,複数の画像・映像を表示するディスプレイを開発した.このディスプレイは一つのパターン(点灯や投影)で複数の画像・映像を表示可能であり,それぞれの画像・映像は特定の位置からしか観察できないという高い指向性を有している.本講演では,この技術を用いて作製した3Dクリスタル,LED型および糸型のボリュームディスプレイについて紹介する. |
||
| 第101回 | 2018/5/31 (木) |
上地 泰一郎 (千葉大学) |
| 要素円が構成する領域の拡大によって要素の見えの大きさが縮小する | ||
|
複数の要素刺激円の呈示される領域の拡大にともない要素の見かけの大きさが縮小する錯視現象を報告した(Uechi & Ichikawa,
VSS2016).本研究では,要素としての円刺激の個数と大きさ,円刺激が構成する領域の大きさ(偏心度)を操作し,これらの要因が要素の見かけの大きさにどのような影響を及ぼすのか調べた.実験1では,円刺激の個数(2~6)と大きさ,その呈示位置(偏心度)を個別に操作し,円刺激の偏心度が大きくなるに従って,全ての個数条件で円刺激の見かけの大きさが縮小すること,円刺激の個数が多い方が縮小の程度が顕著になることを見出した.
実験2では,円刺激の個数(1,2)と大きさ,呈示位置(偏心度)を組み合わせ,円刺激の見かけの大きさの縮小を引き起こす要因が円刺激の呈示位置なのか,要素が構成する領域の拡大なのか,あるいはその両方なのか検討した.円刺激の個数によらず,偏心度の拡大に応じて見かけの大きさの縮小が示された.さらに,円刺激が小さいほど偏心度の拡大に伴う見かけの大きさの縮小の程度が顕著になることを見出した.円刺激が構成する領域の拡大は刺激までの観察距離の縮小を意味する.ところが,この際,円刺激の網膜上の大きさは変動しない.そのため,「大きさ−距離不変仮説」に基づき,大きな偏心度の領域に呈示された円刺激は,観察距離が小さいのに網膜上の大きさが同じということで,要素が縮小して知覚されたと考えられる.他方,単一の刺激呈示でも円刺激の大きさが縮小したことからは,刺激呈示位置の偏心度の拡大による円刺激の見かけの大きさの縮小が,偏心度に応じた視覚皮質における受容野の拡大による処理精度の低下(Carrasco
& Frieder,
1997)に基づいても生じた可能性が考えられる.実験2では,小さい刺激ほど領域拡大による円刺激の縮小の程度が大きいという円刺激の大きさの効果が認められた.この効果については,要素の大きさが小さく,刺激までの距離が比較的大きいことが意味された場合ほど,領域拡大の意味する円刺激までの距離の短縮の程度がより大きくなることで生じた可能性が考えられる.
|
||
| 第100回 | 2018/3/29 (木) |
塩入 諭 (東北大学 電気通信研究所) |
| 注意の無意識性 | ||
|
注意の研究において、注意をどのように定義するかは、大きな問題になりうるが、心理物理的研究においては、実験で求められた処理の促進効果に基づいて注意を定義することで定義の問題を回避している。これは、人間を対象とした脳機能の研究において最も妥当な定義であると考えられる。しかし、この定義が不自然と考えられる状況となる場合もある。自覚的には注意を向けていないところで、注意効果が得られた場合、それは無意識のあるいは潜在的な注意となり、注意を向けていないという主観と矛盾する。本講演では、視覚的注意に関するいくつかの実験的研究から、この無意識な注意効果をどのように捉えるべきかについて検討する。 |
||
| 第99回 | 2018/2/21 (水) |
梯 絵利奈 (千葉大学 工学研究科 デザイン科学専攻・博士後期課程) |
| クラスタリングに基づくアゲハチョウ科の色彩分析 | ||
|
筆者らはこれまで、主観的な代表色抽出によってアゲハチョウ科の色彩傾向を調 査してきた(梯,笠松 2015)。本研究ではより客観的なデータを得るため、類似
画像検索技術を応用したアゲハチョウ科の色彩分析を目的とした。具体的には、 Histogram Intersection(swain 1991)を用いて画像間の類似度を算出し、1-類
似度を画像間の距離として階層的クラスター分析の変数に用い、108枚の蝶画像 を分類した。各クラスターの画像群から、CIELChのヒストグラムを作成し、各属
性の分布特性を分析した。その結果、アゲハチョウ科の蝶の色彩からは主に次の 傾向がみられた。(1)明度が低く、明度差が開いた配色が多い。(2)彩度が低い配
色が多い一方で、彩度差が開いた配色も一部みられる。(3)色相は橙?緑が多く、 これらの補色がわずかに分布する。 |
||
| 第98回 | 2018/1/5 (金) |
Maria Olkkonen, Toni Saarela, Ivana Ilic, Eiji Kimura, Midori Tanaka, Yoko Mizokami |
| 特別企画:色覚と質感セミナー | ||
| 詳しくはコチラ,ポスターはコチラ Date: January 5, 2018 (Fri) 11:10 – 16:10 Place: Chiba University, Engineering Research Building 2 Conference Room (千葉大学西千葉キャンパス工学系総合研究棟2 2階コンファレンスルーム) 11:10 - 11:15 Opening 11:15 - 12:00 Maria Olkkonen (Dept. of Psychology, Durham Univ.): Is it green or blue? How memory and learning shape color perception 13:00 - 13:45 Toni Saarela (Dept. of Psychology, Univ. of Helsinki): Surface material discrimination and cue integration 14:00 - 14:25 Ivana Ilic (Dept. of Psychology, Univ. of Nevada, Reno): Contrast adaptation and artificial lighting 14:30 - 14:55 Eiji Kimura (Faculty of Letters, Chiba Univ.): Biased averaging of colors in multicolored textures 15:00 - 15:25 Midori Tanaka: (Collage of Liberal Arts & Sciences, Chiba Univ.) A shitsukan reproduction approach on display device 15:30 - 15:55 Yoko Mizokami: (Graduate School of Engineering, Chiba Univ.) Shitsukan perception influenced by the diffuseness of lighting 15:55 - 16:10 General Discussion & Closing |
||
| 第97回 | 2017/11/30 (木) |
緑川 晶 (中央大学 文学部) |
| 認知症発症後の感覚・認知・社会的な変化 | ||
|
認知症は早期発見や早期治療が大事だと言われ、これまでの神経心理学なアプローチにおいても、エピソード記憶や遂行機能などの認知機能障害に焦点が当てられ、
健常老化と認知症との鑑別あるいはその早期発見に注力されてきた。しかし実際には、そのような機能低下の影に隠れて、知覚や感覚あるいは認知や社会的機能において、
ときに亢進あるいは向上することが確認される。本講演では、そのような亢進/向上としての変化が生じた自験例を提示するとともに、特に前頭側頭型認知症や緩徐進行性失語症において みられる変化について紹介する。 |
||
| 第96回 | 2017/10/31 (火) |
山田 真希子 (量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所) |
| 認知バイアスの脳内機構 | ||
|
私たちの思考は、偏ったものの見方や思い込みなど「認知バイアス(偏り)」が生じやすい。特に、自分自身に対しては、概して自分に都合の良い解釈を行う傾向があり、「ポジティブ錯覚」と呼ばれる認知バイアスを持つ。ポジティブ錯覚は未来への希望につながることから、こころの健康に重要な役割を果たすと考えられており、うつ病患者は自分について現実的、あるいは、否定的な捉え方をすることが知られている。本講演では、血流の変化を指標として脳の活動領域を調べる機能的脳画像(functional
Magnetic Resonance Imaging:fMRI)と、神経伝達物質の動態を指標とする陽電子放射断層撮影装置(Positron Emission
Tomography:PET)を用いて、健常者のポジティブ錯覚が脳内で生じる仕組みについて解説し、絶望感、潜在的自己意識、うつ病との関連を議論する。 また、認知バイアスは、例え客観的事実を知らされたとしても、修正されにくいという特徴を持つ。つまり、自己の思考や知覚経験に対する確信はそれほど確固とした意識体験なのである。このような「自己の経験への信念」の脳内における生成メカニズムを解明することで、錯覚や、幻覚、妄想の病態理解に繋がる可能性が期待できる。本講演の後半では、視知覚の変容と確信感を支える脳機能と分子機構についての我々の研究を紹介する。感情が主観的時間の長さに影響を与えることが知られている。しかし、その影響が記憶・検索段階で生じているのか、知覚の時間精度に関わる段階で既に感情の効果があるのかについては、まだわかっていなかった。感情が知覚の時間精度に関わる段階に与える影響を検討するために、本研究ではカラー画像を短時間白黒に変化させ、白黒画像を知覚できる最短の提示時間を測定した。写真画像集IAPSから危険な画像と安全な画像を選出し実験を行なったところ、危険な画像の方が安全な画像よりも主観的時間が長くなること、視覚の時間精度も高くなることがわかった。また、実験2では画像の感情条件を増やし、実験3では情景画像ではなく、顔画像の表情を用いて感情の操作を行い、視覚の時間精度が上昇する条件について検討を重ねた。これらの実験結果を紹介し、感情が視覚の時間精度に与える影響について整理する。 |
||
| 第95回 | 2017/9/21 (木) |
小林 美沙 (千葉大学 人文公共学府 人文科学専攻 心理学コース・博士前期課程) |
| 色字共感覚における共感覚色の決定過程 | ||
|
感情が主観的時間の長さに影響を与えることが知られている。しかし、その影響が記憶・検索段階で生じているのか、知覚の時間精度に関わる段階で既に感情の効果があるのかについては、まだわかっていなかった。感情が知覚の時間精度に関わる段階に与える影響を検討するために、本研究ではカラー画像を短時間白黒に変化させ、白黒画像を知覚できる最短の提示時間を測定した。写真画像集IAPSから危険な画像と安全な画像を選出し実験を行なったところ、危険な画像の方が安全な画像よりも主観的時間が長くなること、視覚の時間精度も高くなることがわかった。また、実験2では画像の感情条件を増やし、実験3では情景画像ではなく、顔画像の表情を用いて感情の操作を行い、視覚の時間精度が上昇する条件について検討を重ねた。これらの実験結果を紹介し、感情が視覚の時間精度に与える影響について整理する。 |
||
| 第94回 | 2017/8/3 (木) |
濱田 大佐 (京都大学/日本学術振興会特別研究員) |
| 色字共感覚における共感覚色の決定過程 | ||
|
少数の人には文字知覚が色の体験を生じさせる色字共感覚と呼ばれる現象が存在する。どの文字にどのような特定の色 (共感覚色)
が結びつくのかは共感覚者間で多様であり、個人特異的である。このような個人特異性に対して、近年では共感覚者間に共通する共感覚色の規定因を探る試みがなされており、様々な文字要因が共感覚色の決定に寄与することが報告されてきている。しかし、文字要因の検討だけでは共感覚色の決定の一部しか説明できていないという問題がある。そこで本研究では、文字要因のより詳細な検討に加えて、共感覚色の決定に関わる知覚特性に着目して、二つの異なる視点から共感覚色の決定に関わる諸特性を明らかにすることを目的とした。
研究1では文字要因の視点から、共感覚色の規定因の個人差が共感覚色の主観的経験によって反映される文字処理の傾向の違いで説明できるかどうかをマルチレベル分析により検討した。研究2では共感覚色の知覚特性の視点から、「共感覚色になりやすい色があるのか」という根本的な問題を取り上げた。より具体的に、共感覚者一人に多くの共感覚色データを収集し、空間統計学の手法を用いて色度座標上での共感覚色の分布パターンを解析した。研究3では、共感覚色の決定にどのような知覚特性が関与しているのかを明らかにするために、共感覚色と物理色感度の対応関係を検討した。
その結果、1) 共感覚色の規定因は共感覚者の文字処理の傾向の違いによって部分的に決定されること、2) 共感覚色はランダムに決定されるのではなく、共感覚者ごとに特定の色領域から選択的に決定されること、3)
共感覚色の決定には物理色の感度が関与する可能性が示された。 |
||
| 第93回 | 2017/7/26 (水) |
大住 雅之 (株式会社 オフィス・カラーサイエンス) |
| 最近の色彩・質感計測機器と測定の実際 | ||
|
インダストリアルデザインに於ける質感の重要性が謳われて久しい.最近の工業製品や工芸品は,特殊な光学特性を備えた材料や複雑な表面加工・処理を施す事によって,多様な質感を表現している.このような背景の中,製造上の品質管理には,質感に関連する高次元の情報を,容易に計測できる機器が必要となり,統合アピアランス計測の関心が,製造現場を中心に高まっている.本講演では、最近の計測に機器について,その動向と共に原理や多くの計測例を紹介する.また,測色システムと光学幾何条件,及び質感との関係や,材料と表面構造に関する最近のトピックを取り上げる.特に自動車塗色に関しては,CIE2016年のプラハ大会で,多くの研究者が使用しているポータブル分光光度計(BYK
Gardner社 BYK mac i)を持ち込み,計測の実際を理解して頂くと共に,質感に関する計測のアプローチについて,実際の工業生産の側面に立って解説を行う. |
||
| 第92回 | 2017/6/14 (水) |
大倉 典子 (芝浦工業大学 工学部 情報工学科) |
| バーチャル環境と実環境を併用した、樹脂表面の質感の感性評価 樹脂表面の印象に与える質感 | ||
| バーチャル環境と実環境を併用した、樹脂表面の質感の感性評価
樹脂表面の印象に与える質感(視覚的質感と触感)の影響を明らかにする目的で、バーチャル空間内の異なる色相の3Dモデルと、異なる粒子径のビーズを塗布した樹脂を側面に巻きつけた円柱状の実物体とを用い、年代や性別の異なる実験協力者を対象として、種々の形容詞対による感性評価実験を行った。実験結果を重回帰分析やクラスター分析等で解析し、色相、ビーズの粒子径、実験協力者の性別、年代による感性評価への影響を明らかにした。
ここでは、「評価対象とする形容詞対の選定実験」と「対象とする色相の選定実験」に簡単に触れた上で、最終実験について詳しく紹介する。 |
||
| 第91回 | 2017/4/20 (木) |
小山 慎一 (千葉大学 大学院 工学研究科デザイン科学専攻/(2017年4月より)筑波大学 芸術系プロダクトデザイン領域)) |
| 実験心理学的手法による医薬品・食品パッケージデザインの研究 | ||
|
筆者らの研究グループは実験心理学的アプローチによる医薬品表示デザインの研究を推進してきた.視覚探索課題や視線追跡,チェンジ・ブラインドネスといった知覚心理学的研究方法を応用し,医薬品のパッケージデザインにおける消費者の視認性や情報理解,好ましさに関する基礎的な知見を得るとともに,それらを反映させたパッケージデザイン開発を行った(例:崔ほか,
2012; 蘇ほか, 2009).一連の研究の主な成果はイラストを用いたわかりやすい表示デザインの開発であったが(朴ほか,
2014),研究の過程でこのような視覚的にわかりやすい表示のもつ弊害も次第に明らかになってきた.すなわち,ブランドやロゴ等の「わかりやすいシンボル」が商品上に表示されている場合,消費者は「わかりやすいシンボル」に過度に依存した商品選択を行うようになり,詳細な情報や商品そのものを見なくなる危険性が示唆された.本発表では筆者らの研究を紹介するとともに,実験心理学的手法をデザインに応用する意義について考察する. |
||
| 第90回 | 2017/3/22 (水) |
Prof. & Dr. Hiroshi Ono (York University) |
| Revisiting Cyclops and his Eye | ||
|
略歴:1936年京都市生.ダートマス大学卒,スタンフォード大学において学位を取得後,ハワイ大学を経て今日に至る. 案内:両眼による空間視の研究を行っているカナダの心理学者Hiroshi Onoを招き,サイクロピアン・アイをテーマとしてセミナーを開催します. サイクロピアン・アイとは,両眼(2つの光学的原点)を使って物を見ているにもかかわらず,その物の視方向が特定の方向に見える(視覚的原点は1つ)現象です. セミナーでは,心理学,認知科学のさまざまな研究者間の積極的な意見交換を歓迎しています.日本語と英語が混在したセミナーになります.気軽にご参加ください. 主催 千葉大学MAISプロジェクト,千葉視覚研究会 . |
||
| 第89回 | 2017/3/3 (金) |
Qian Qian (Yunnan Key Laboratory of Computer Technology Applications, Kunming University of Science and Technology) |
| Cueing and sequential effects in visual spatial orienting paradigm | ||
| Visual spatial orienting paradigm has been
widely used to investigate
the attention orienting induced by visual cues, like peripheral onsets,
central arrows or gazes. Cueing effects refer to the RT facilitation between
cued and uncued trials, and sequential effects refer to the RT facilitation
when cue validity (cued or uncued) repeats between trials. This presentation
focuses on the attention mechanisms under the cueing effects induced by
gaze cues and the sequential effects induced by uninformative arrow cues.
As for the cueing effect, the findings suggest that gaze-cueing effects
are based on mechanisms specialized for gaze perception, and the magnitude
of gaze-cueing effects is probably a function of the perceived gaze direction.
As for the sequential effect, the findings suggest that sequential effects
are probably based on implicit memory mechanisms (automatic retrieval or
feature-integration), and are sensitive to the spatial organization conditions
of targets and cues. |
||
| 第88回 | 2017/2/2 (木) |
仲谷 正史 (北海道大学 電子科学研究所) |
| 音響信号を利用した触質感提示の試み | ||
|
ウェアラブルデバイスやスマートフォンへの触覚フィードバック手法の開発を皮切りに、触覚ディスプレイ(さわり心地を電子的に記録し、再現する技術)の研究成果が社会に広く認知されるようになってきた。講演者は、これまで、音響信号を振動に変換して触感を体験させる技術:テクタイルツールキットの開発に携わり、多種類の触質感再現の事例を集めてきた。本発表では、触知覚・振動感覚の基礎知見についてふれながら、触振動感覚で表現できる触質感について技術デモとともに論じる。 |
||
| 第87回 | 2016/12/7 (水) |
方 昱 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| 単眼性のマイクロサッカードは存在するのか? | ||
| Microsaccades are small and fast ballistic eye
movements occurring during
fixation. Microsccades have been suggested with similar function with larger
sacccades, which occurre simultaneously in both eyes and are always binocular
(Collewijn & Kowler, 2008). However, some investigators reported that
monocular microsaccades exist with a proportion of more than 10% to 40%
of microsaccades (Gautier, Bedell, Siderov, & Waugh, 2016). We examined
microsaccades made with DPI eye-tracker under head-fixed condition, and
the data set made with search coil under head-free condition, respectively.
Our results revealed that only one microsaccade was classified as monocular
microsaccade in both conditions while the threshold of peak speed ranged
from 5 to 15 deg/s. The results show that there is no evidence to suggest
the existence of monocular microsaccade. |
||
| 第86回 | 2016/11/10 (木) |
渡辺 安里依 (千葉大学 文学部) |
| Peeping birds: Using observational spatial memory tasks to study avian metacognition | ||
| It has been claimed that metacognition, or the
ability to think about
one’s own thoughts, is unique to humans. Despite the difficulties of testing
metacognition in nonverbal subjects, evidence has started to accumulate
that this ability may also be shared by some of the other primate species.
In this talk, I will introduce another candidate for possessing this ability
– western scrub-jays. Although their physical structure and evolutionary
history are very different from humans, these birds are known to be capable
of solving tasks that require complex cognition. To test their metacognitive
ability, they were presented with a series of tasks that require assessment
of contents stored in their memory. Each task involved the birds observing
a human experimenter hide food at one of multiple locations and, then,
choosing a location to search. I will discuss the results in light of their
caching behaviour and observational spatial memory. |
||
| 第85回 | 2016/8/3 (水) |
永登 大和 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 他者の視線が観察者の注意に及ぼす影響と個人差に関する研究 | ||
|
他者の視線には社会的な相互作用を円滑に行うための情報が多く含まれており、我々は視線方向から他者の注意の対象や意図、心情を推測することができる。視線が観察者に及ぼす影響について検討した先行研究では、視線の方向へと観察者の注意が定位することが明らかになっている。視線の方向推定の精度が目の領域のコントラストを逆転させると低下することから、虹彩と強膜の位置関係が明確に分かるためのコントラストや形態が視線の認知に重要であるとされている。また、この注意効果には性差や、自閉症スペクトラム指数(AQ)との関連が認められており、視線に独特の社会的なメカニズムによる処理が示唆されているが、視線の認知の個人差を規定する要因は未だ不明確である。本発表では、視線を認知するために、「目」のどのような要素が重要であるか、また、視線方向によって生じる注意効果の特性や個人差から、社会的な刺激としての視線の独自性について、先行研究と発表者の研究を踏まえて考察する |
||
| 第84回 | 2016/8/3 (水) |
徳永 留美 (千葉大学 国際教養学部) |
| 目撃証言における顔色の表現と証拠能力 | ||
|
目撃者証言において、犯人の視覚的表現を述べる際に顔色がある。裁判においても、犯人の顔の色名が争点となる場合がある。しかしながら、表現された顔色の証拠能力は低い。目撃者証言の多くが記憶した色を述べるが、そもそも私たちはどのような色名で顔の色を表現し、安定した色名による応答が可能なのだろうか。さらに、裁判員制度を考慮すると、目撃者証言の「顔の色名」と、その色名から裁判員が想起する色の対応関係を把握することは重要である。そこで本研究では大学生を対象とし、まず、顔の色名のバリエーションを調査し、色名のカテゴリーと応答の恒常性について検討した。そして、前述の結果をもとに、全被験者が使用した色を基に25色の「顔の色名」を選択し、「顔の色名」と「顔の色名」から想起する色の整合性について検討した。 |
||
| 第83回 | 2016/6/30 (木) |
向井 志緒子 (千葉大学 大学院 工学研究科・博士後期課程) |
| 商品パッケージデザインにおける構成要素同士の印象評価の類似性が商品の美的印象へ与える影響 | ||
|
日常生活において,我々は商品パッケージを構成する広告的要素(ロゴ,色彩,商品コピー等)から様々な印象を受け取っている。それぞれの要素は相互に影響しながら消費者の印象に影響するといわれるが,特に要素同士の類似性が商品評価に良い影響を与えることが知られている。しかし,類似性を同定するための客観的な評価方法や,類似性が商品の印象評価向上を喚起するプロセスについてはこれまで検討されていない。 本発表では,まず,お茶飲料商品のパッケージデザインと和文書体フォントデザインの印象評価調査を実施した結果を用いて客観的な類似性評価を示唆した研究を紹介する。次に,同様のパッケージとフォントデザインを用いた評価実験の結果から,どのような心理プロセスを経て商品の美的印象に影響するのかを示唆した研究を紹介する。これらの結果より,類似性がもたらす商品の美的印象には可読性評価が重要な情報であることを示唆した。 |
||
| 第82回 | 2016/6/2 (木) |
河村 康佑 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 他者の痛み観察時の不快感を喚起する要因の検討 | ||
| 我々は日常生活において, 痛みを体験している他者を観察した時,
自らは痛みを体験していないにも関わらず, 不快感が生じる。こうした現象は「痛みの共感」と呼ばれ,
他者とのコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしているとされる。他者の痛み観察時の不快感を検討した先行研究では, 包丁で手を切る等の痛みを生起する事象
(痛み事象) と, 痛みを表出している表情 (痛み表情) のいずれかが用いられてきた。しかし, 他者の痛み観察時の不快感喚起における両者の寄与の程度はこれまで検討されていない。本発表では,
まず, 痛み事象と痛み表情を同画面内に収めた動画を用いて検討し,痛み事象の優位性を示した研究について紹介する。次に, 痛み事象によって生じうる創傷の観点から,
痛み事象観察時の不快感の程度を規定する要因を検討した研究について紹介する。また, 質問紙における個人差指標との関連性から, 他者の痛み観察時の不快感喚起の背景にある要因についても考察する。 |
||
| 第81回 | 2016/4/27 (水) |
田中 緑 (千葉大学 国際教養学部) |
| 実物体と画像を用いた質感解析に関する研究 | ||
|
ヒトの知覚・認識、画像工学などの様々な分野の研究において、質感(材質の見え)が注目を浴びている。
それらの研究の多くは、実物体の刺激やモニタに表示された画像刺激が用いられているが、
それらの関係性については明らかにされていない。
本研究の目的は、実物体と再現画像を用いて、知覚される質感の違いを解析することである。
本発表では、2種類の実験について紹介する。
第1の実験では、実物体と再現画像を用いた材質の見えに対する質感属性の違いを調査し、
刺激呈示方法の違いが質感の知覚に影響を及ぼし得ることを明らかにした。
第2の実験では、実物体と再現画像を用いて材質の見えの調和の違いを調査し、
刺激呈示方法や材質の観察条件の違いが、質感の調和に影響を与え得ることを明らかにした。
|
||
| 第80回 | 2016/3/24 (木) |
Sérgio Nascimento (Universidade do Minho) <特別講演> |
| Seeing colors in nature ? what do we learn from spectral imaging | ||
| Colors seen in nature are determined by the
spectral and spatial properties
of objects and illumination. Given the complexity of natural stimuli these
properties are best evaluated by spectral imaging, a technique that records
the reflecting spectral profile from each point of a scene. This talk will
discuss several applications of this technique in colorimetry, e.g. the
gamut and distribution of natural colors for normal and for color deficient
observers, chromatic distortion due to atmospheric conditions and the variations
of the spectral composition of the illumination across scenes. Spectral
imaging data can also be used to synthetize stimuli for psychophysical
experiments. It will be shown how these stimuli can be used to estimate
the number of principal components necessary to reproduce reliably natural
scenes and to measure a threshold for perceptibility of color differences
in reproductions of natural scenes. Applications to color rendering will
also be explored, in particular, those concerning the study of lighting
optimization for artistic paintings, food displays and color deficiencies.
Other applications in art will also be discussed. |
||
| 第79回 | 2016/3/14 (月) |
今泉 修 (千葉大学 大学院 工学研究科・博士後期課程) |
| 集合体への嫌悪に関わる視覚刺激特性と性格特性 | ||
|
円形や物体の集合体(例:蓮の種)に嫌悪や不快を感じることがあり,こうした反応をトライポフォビアと呼ぶことがある。その嫌悪の強度の個人差も示唆されている。トライポフォビアの機序として,空間周波数特性からの説明や,有毒生物や人体損壊の連想からの説明が提案されている。本発表は,どのような視覚刺激特性がトライポフォビアを誘発するかについて,空間周波数や集合体密度や被写体などの観点から検討した先行研究と我々の研究を紹介する。また,どのような性格特性がトライポフォビアの個人差を説明するかについて,心理尺度を作成したうえで嫌悪感受性や共感性などの観点から検討した我々の研究を紹介する。 |
||
| 第78回 | 2016/2/22 (月) |
菊地 久美子 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 肌の明るさ知覚に影響を及ぼす色素斑の特徴理解 | ||
|
顔に生じる色素沈着(いわゆる,シミ)は肌の加齢特徴の一つであり,他者に与える印象を大きく左右することが知られている.色素沈着の大きさ・色調は様々であり,また頬に生じる数も影響して,頬部は様々な状態を呈する.頬部画像の特徴量を利用し,肌の不均一性と印象の関係について調査した例は複数挙げられるが,数・面積・色調など,色素沈着の分布を特徴付けるパラメータと,知覚との関連については明らかになっていない.
本研究は色素沈着の分布を特徴付けるパラメータ(頬部における数・面積・色調・正常部位の肌色)と頬部の「色素沈着部位の目立ち」および「正常部位の肌色の明るさ」の知覚の関係について明確にすることを目的とする.まず,頬部の画像の視感評価値と,画像から算出される色素沈着の分布パラメータに対しPLS回帰分析を行い,関連の強いパラメータを抽出する.次に,色素斑の個数,面積および色彩値の各パラメータを独立に変調させた画像を人工的に作成し,「色素斑の目立ち」および「正常部位の明るさ」の知覚に対する影響の程度について明確化する. |
||
| 第77回 | 2015/12/17 (木) |
Philip Grove (University of Queensland) <特別講演> |
| Single and double vision in the central binocular field | ||
| The human visual system receives input from two
laterally separated forward
facing eyes. The result is that the two eyes .F N" retinal images contain slight image differences, called
disparities. Wheatstone (1838) famously
demonstrated the importance of disparities for depth perception by presenting two 2D images corresponding the
left and right eyes N" view of a 3D object
that yielded a vivid impression of three-dimensional volume. Over a limited range, binocular disparities
underlie vivid and precise stereoscopic depth perception
accompanied by single vision. Outside this range, double vision ensues and stereoscopic depth perception is
degraded. I will present results
from four recent studies examining the conditions under which single and double vision are experienced. These
experiments provide updates
for existing accounts of binocular correspondence and the distribution of fusible disparities in the central
binocular field.
I will also link these results to specific applications of stereoscopic imaging such as 3D television, cinema,
and surgical interfaces. |
||
| 第76回 | 2015/11/12 (木) |
米村 朋子 (明海大学 総合教育センター/専任講師) |
| 身体運動の随意性保持と自他弁別要因の検討 | ||
|
我々は歩いたり,手で物を動かしたりする際に,風景や操作対象の視覚的運動情報を手掛かりとして,自分の動きを認識したり身体の制御を行っている.自己運
動と視覚の変化が同期しているという随意性がある(視覚運動協応がある)と認識できる状況では,自己運動の知覚に疑問を持つことはない.一方,随意性が突
然失われてしまった場合,それが自己運動によるものなのか,自己以外(他者/環境)の影響なのかという自他判断が求められる.本発表では,身体運動の随意
性が保持される範囲を明らかにするための一連の研究成果を報告する.実験では,自己の身体運動と同期した視覚対象の運動速度や見えの連続性を,運動途中
で操作した際の身体運動の変容を分析した.その結果,自己運動と視覚的運動の随意性が損なわれた場合でも,一定の範囲内において,随意性を保たせるように
身体運動が制御される段階が存在することがわかった.結果を踏まえ,自己運動知覚および運動制御の生起メカニズムにおける自他弁別要因について議論したい. |
||
| 第75回 | 2015/10/28 (水) |
Miguel Angel Martinez-Domingo (PhD. student at University of Granada) |
| High dynamic range scientific imaging: Advantages and limitations | ||
| When we use imaging systems for scientific
purposes, one fundamental and
important step during the capture process is the selection of the exposure
settings. This is not a trivial task, specially if we deal with high dynamic
range scenes. We have proposed an algorithm to estimate automatically the
bracketing set needed to capture the whole dynamic range of a scene. Many
authors have proposed methods to build a high dynamic range radiance map
from a scene by mapping camera response values to integrated radiance from
each point of the scene. They support this assumption, assuming that the
reciprocity law always holds when capturing an image. However, when we
deal with real imaging systems, building a trustworthy radiance map of
our scene is a challenging task. This is due to the presence of optical
phenomena such as veiling glare which escape our control and make our imaging
system violate apparently the reciprocity law. Some examples about them
will be shown and commented. |
||
| 第74回 | 2015/9/18 (金) |
森本 拓馬 (東京工業大学 大学院 総合理工学研究科・博士前期課程) |
| オプティマルカラー仮説に基づく照明光推定 | ||
|
照明光の変化によらず,我々は物体表面の色を安定して知覚することができる.色恒常性として知られるこの性質が成り立つためには,シーン内の何らかの手がかりを用いて照明光を推定する必要がある.分光反射率0%または100%のみで構成される表面はオプティマルカラーと呼ばれ,ある色度における最大明度をとる.従って,ある特定の照明光の元で存在し得る色度と輝度の範囲はオプティマルカラーの集合により表現することができる.本研究ではシーンが作る色度と輝度の範囲に対し,視覚系が最もよく合うオプティマルカラー分布を選択して照明光を推定しているというオプティマルカラー仮説を立て,その有効性を心理物理実験により検討した.本発表では他の色恒常性モデルと比較を行いながら,本仮説の妥当性について紹介する. |
||
| 第73回 | 2015/7/9 (木) |
Dr. Hannah Smithson (Department of Experimental Psychology, University of Oxford) <特別講演> |
| Colour in light and materials | ||
| The spectral energy distribution of the light
that enters our eyes carries with it signatures of physical interactions between light and the materials
around us. I will present three projects that investigate the perceptual consequences of these interactions.
The first explores the use of specularity to separate illumination and reflectance for single surfaces―the
“shiny balls experiment”. The second reports perceptual discriminations of scatter and absorption in
liquids―the “tea experiment”.
The third describes a co-ordinate system for colour based on scatter in natural rainbows ―the work of a 13th
century scholar. All three projects make use of computer models of the interactions between light and
materials to generate stimuli that have only recently been available to perceptual science. The last project
however was directly inspired by observations made over 750 years ago that put material properties at the
centre of the discussion on colour.
|
||
| 第72回 | 2015/6/4 (木) |
宍倉 正視 (DIC株式会社) |
| 特色印刷インキ赤色の見えに関する評価-各色覚タイプにおける照明条件の影響- | ||
|
食料品や薬製品等の包装印刷では、新聞や雑誌等で主に使われているCMYK4色のプロセスインキよりも、インキ自体を混ぜ合わせて調色する特色インキを使用するケースが多い。特色インキは複数の基本インキを組み合わせて配合調整することにより目標色の色再現を実現するが、基本インキの組み合わせは必ずしも一意ではなく、同じ目標色を再現する組み合わせ候補が複数存在する。従来、それら複数候補の中から特定の基本インキ組み合わせを選ぶ基準としては、耐光性などの物理的特性によるところが大きい。しかし、包装印刷においては、それら物理的特性だけではなく、製品イメージとしてのデザイン性や製品に関する注意事項などを消費者に伝えることも重要な特性である。このため、基本インキの組み合わせを選ぶためには、“色の見え”という心理物理的特性からの判断基準も必要である。特に、赤色インキは注意事項を表記することが多いため、様々な照明条件や色覚タイプにおける色の見えが重要である。
本研究会では、基本インキの組み合わせ方を変えた特色赤色インキを対象に「赤らしさ」および「黒背景での見分けやすさ」の各色覚タイプにおける照明条件の影響評価実験について紹介し、今後の展開について議論したい。
|
||
| 第71回 | 2015/4/23 (木) |
岡崎 聡 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 2純音の同時性の窓~2音の周波数距離の関数として~ | ||
|
人はある程度ずれた2音を同時と判断する。この同時と判断される非同時の区間を「同時性の窓」と呼ぶ。本研究は初めて,2純音の同時性の窓が,2音の周波数距離の関数として,どのように変化するか検討した。 本発表では,まず,従来の2音の同時性判断課題において,2音の融合・分離判断が混在し得ることを示す。このことが,同時性知覚の特性についての精密な測定を妨げていた可能性を指摘する。次に,2音の同時性の窓の大きさと2音の間の周波数距離の量的な関係を報告し,この関係を蝸牛基底膜振動および聴神経の発火パターンを用いて説明する。最後に,本研究が提唱する説明の妥当性を確認するため行った検証実験の結果を報告する。 |
||
| 第70回 | 2015/3/13 (金) |
勝田 徹 (国立歴史民俗博物館 管理部 博物館事業課・専門員) |
| 文化財写真の撮影の実際 | ||
|
話者は昭和59年から現職にあり,館蔵資料を中心とした歴史・考古・民俗資料の写真撮影ならびにそれらの保存管理を手がけ、フィルム時代からデジタル時代の文化財写真のあり方をにらみつつ日々業務に従事している.また、文化財写真技術研究会
http://www.maishaken.jp (旧 埋蔵文化財写真技術研究会)に長年参画し、文化財写真の普及啓蒙にも尽力している。 講演概略: 文化財写真の特徴として、以下のようなことがあげられる。 1.有形・無形文化財を今現在の写真技術を使い撮影し作る写真である。 2.精緻で正確かつ明瞭な情報量豊かな記録写真である。 3.将来にわたり、研究者など利用者の使用に耐えられるように保存管理を必要とする。 撮影に際しては、その資料の持つ特徴をできるだけ明確に表現しようと試みる。多くの場合、撮影対象の資料の専門家である研究者と共に撮影に臨み、その方々の専門的意向をできるだけ表現できるように心がけている。 今回は,国立歴史民俗博物館において年1回全国の歴史民俗資料を取り扱う博物館関係者を対象に開催している歴史民俗資料館等専門職員研修会での講義内容を中心に,文化財写真の考え方や撮影について、実際のプリントを見ていただき、どのように撮影しているかをお話ししたい。 |
||
| 第69回 | 2015/2/5 (木) |
奥村 治彦 (東芝,千葉大学客員教授) |
| 高臨場感ディスプレイの研究:-片目で奥行きを感じさせる単眼表示技術- | ||
| 最近、Google GlassやOcculas
Riftなど拡張現実感(AR)や仮想現実感(VR)が注目されているが、そのためのディスプレイ技術としては、リアルな空間と区別がつかないような仮想空間を実現することが重要になる。このような仮想空間を人間の脳内に作り上げるためには、人間の視野全体を覆うような広視野ディスプレイと奥行感を感じさせる表示技術の研究開発がもっとも重要と考えられる。今回、広視野ディスプレイとして、人間の視野に相当する160度以上の視野をもつドームタイプディスプレイを開発するとともに、それを用いて人間の奥行感を測定したところ、両目ではなく、片目にだけ表示したほうが奥行感が得られるという新たな結果が得られた。さらに、この単眼表示技術を利用して、車載用シースルー型ディスプレイ(単眼ヘッドアップディスプレイ:HUD)を試作し、仮想ナビ矢印をリアルな空間に重畳表示することにより、100m先のナビ情報を正確に、かつ直観的に伝えることができることを実証した。これらの結果とともに、単眼の疲労感や注意広がり特性など、さまざまな単眼特性について紹介する。 |
||
| 第68回 | 2014/12/10 (水) |
村越 琢磨 (千葉大学 文学部) |
| 変化の検出と変化の位置判断のメカニズム | ||
|
変化検出には変化そのものの検出に加え,変化がどこで生じたかの位置判断,どのような変化が生じたかの変化内容の同定が存在する.従来の変化検出研究では,変化を検出するためにVSTM
(visual short-term
memory)内の詳細な表象の検索・比較が必要であると考えられてきた.この考えに基づくと,変化が検出された場合には,その変化の位置判断や変化内容の同定まで可能となる.しかしながら,我々を取り巻く環境では常に変化が生じており,常に詳細な表象を形成し,変化を検索・比較することは非効率的である.そこで,本研究では視覚系は二段階の処理によって変化を検出するというモデルを提案する.このモデルでは,視覚系はまず,視覚場面の全体情報を利用し,視覚場面間に変化が生じたか否かだけの粗い変化を検出する.視覚場面間に変化が存在することが検出されると,その後,VSTM内の表象を検索・比較することで,どこで,どのような変化が生じたかの検討が行われる.本研究で提案された二段階モデルを仮定することで,必ずしもVSTM内の詳細な表象を必要とせずとも変化を検出することが可能となる. |
||
| 第67回 | 2014/11/19 (水) |
中島 由貴 (女子美術大学 大学院 美術専攻・博士後期課程) |
| 美術館・博物館における最適な照明・色彩視環境の研究 | ||
|
美術館・博物館では照明光の光放射が原因で生じる美術作品の変退色を抑制するために、美術作品の耐光性ごとに照明条件、特に展示照度が制限されている。CIEでは特に光に弱い美術作品の展示推奨照度を50
lx以下としており、日本画のように光に敏感な画材の場合は低照度下での鑑賞が余儀なくされ、10
lx前後の場合もある。照度の違いは物体色の見えに影響し、Hunt効果によって低照度下では高照度下の色よりも暗くくすみ、色から受ける印象も変化するため低照度下の美術作品鑑賞に問題が生じる。美術館における最適な照明色彩・視環境において“演色性とはどうあるべきなのか”を検討する必要がある。LEDランプを含む各種光源および異なる照度下での物体色の見えの評価、および色の見えの評価に基づく美術館用光源の演色性評価方法の試みについて紹介する。 |
||
| 第66回 | 2014/10/29 (水) |
實森 正子 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| ハトにおける画像知覚と視覚的注意:視覚探索課題と高速逐次視覚呈示法を用いて | ||
| ハトなどの鳥類にとって, 高速で飛行しながら様々な物体を識別したり,
運動している他の物体を迅速に認識することは, 環境適応の上で必須である。高速で空間移動する鳥類は,
視覚情報の高速処理能力もまた進化の過程で獲得したと考えられる。運動刺激の視覚探索(Visual Search) 課題をヒトとハトに用いて得た最近の研究成果を紹介し,
視覚的注意過程とその適応的意義について考察する。また, ハトにも適用可能な高速逐次視覚呈示(Rapid Serial Visual Presentation)
法を開発したので, その研究成果の一部を紹介する。この課題では, 妨害刺激2つと標的刺激1つが各試行で高速逐次呈示され(いずれも鳥の画像),
予め定められた2種類の標的刺激のどちらがその試行で出現したかによって, 赤または緑の比較刺激を選択することが求められた。こうしたRSVP試行において,
標的刺激の同定にハトは約80 msを要することが推定された。一方, 標的刺激の前後に妨害刺激(マスク刺激)が呈示されない条件(Target-only試行)では,
標的刺激を80 ms以下で呈示(>17 ms)しても, チャンスレベルより有意に高い正答率が得られた。これらの結果から, 標的刺激が除去された後もその処理が持続された可能性が示された。 |
||
| 第65回 | 2014/9/16 (火) |
小林 裕幸 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| 私たちは粒状から何を感ずるか | ||
|
ロバート・キャパが撮ったDデイの写真は、そこに写っている光景以上にそのざらついた画質が私たちに緊迫感を感じさせる。ロラン・バルトは母親を亡くしたばかりのある晩、幼い日の母親の写真を構成する銀の粒子に、星から遅れてやって来る光のように、バルトに触れにやって来る「光線の宝庫」を感じた。写真の画像は銀の粒子から構成されており、私たちはそれを意識するしないにかかわらず、その粒状からいろいろな情報を得ている。もちろん、私たちが粒状から何を感ずるかは、私たち個々の体験に依存する。技術者の努力で粒状が無くなり写真プリントと呼ばれるようにインクジェットプリンタの画像は好まれず、皮肉にも銀塩写真同様の粒状を付加するなどの画像処理がなされている。私たちは、この好ましさを感じさせる粒状について、好ましい色再現における記憶色と同様に、「記憶質感」が影響していることを提案している。粒状付加が鮮鋭性を向上させる現象においても、この記憶質感が重要な役割を演じていると考えている。 |
||
| 第64回 | 2014/7/28 (月) |
大武 潤己 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士前期課程) |
| 金属の質感空間構築のための主観評価実験方法について | ||
|
近年,コンピュータグラフィックス技術が発達し,様々な質感をよりリアルに再現することが可能となっている.製作者は物体をCGで表現する際,直感的にわかりやすいLabやマンセルなどの色空間で色を選択し,描写することができる.これらの色空間により,色の判別や描写がしやすくなっている.これは色空間上の数値の変化がそのまま色の変化に対応しており,視覚的に理解しやすいからである.しかし,CGで表現される物体の質感においては明確な指標が存在しないため製作者が経験的に決定している.そこで,色空間のように質感に対する空間が構築できれば,質感表現が容易になり,物体認識やCG技術の発展に寄与できる. そこで本研究では人が感じる金属らしさに着目し,金属質感における空間を構築することを目標としている.この空間の作成手順としてはまず,反射特性に基づく様々なCG画像に対し,主観評価実験を行うことで,各画像がどのくらい金属に見えるのかを測定する.そして,金属空間における軸の変数を明らかにするために実験結果の分析を行っていく. 今回はこの手順における金属質感の空間作成に用いた様々な主観評価実験手法と分析結果に関して考察を行う. |
||
| 第63回 | 2014/6/26 (木) |
大沼 一彦 (千葉大学 フロンティア医工学センター) |
| 眼の中の散乱光測定 | ||
|
白内障になると、明るいところに出たりするとまぶしく、また、夜のヘッドライトがとても大きく見えたりします。これは、角膜、水晶体で光が散乱するからです。この散乱は、正常眼でも起きます。ただ、その強度が低いので、気にならないだけです。 この散乱光の強度および、角度分布を測定する方法には、現在、リング光源とその中心に置いた小さな光源を用いて、フリッカーさせることにより、求めるものがあり、その装置が販売されています。フリッカーを使う方法は、日本では受け入れがたく、それ以外の測定方法が望まれています。今回は、フリッカー以外の心理物理的な方法(私の開発した方法)の紹介と、Ginis HS先生(ムルシア大学、光学研究所、P.Artal先生が研究所長)の開発した物理的に測定する方法の紹介をします |
||
| 第62回 | 2014/5/28 (水) |
辻田 匡葵 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 身体運動-視覚間時間再較正に寄与する処理過程の検討 | ||
|
能動的な身体運動に合わせて一定の遅延を伴った視覚刺激が提示される状況が持続すると,身体運動と視覚との間の時間順序知覚が視覚刺激の遅延を小さくする方向に変化
(再較正)
することが知られている.これまでの研究によって,身体運動と視覚との間で生じる時間再較正は網膜位置特異性を持つような初期的な視覚処理段階ではなく,比較的高次の段階の処理に基づいて生じていることが示唆されてきた.本研究では,身体運動-視覚間時間再較正が注意資源を必要とする処理に依存しているのか検討した.順応期間中の二重課題によって身体運動と視覚刺激との間の遅延に向けられる注意資源を制限された状態において,時間的再較正が成立するのか調べた.この実験の結果から,身体運動-視覚間時間再較正がどのような過程の処理に基づいて成立しているのか考察する. |
||
| 第61回 | 2014/4/16 (水) |
竹下 友美 (DICカラーデザイン株式会社) |
| 「カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット」の取り組み | ||
|
遺伝子の特性の違いや眼の疾患が原因で、色の違いを区別しづらく不便を感じる人が日本に数百万人いると言われている。このような多様な色覚に配慮し、すべての人が等しく情報を認識できるよう、色や色の組合せをデザインすることをカラーユニバーサルデザイン(CUD)と呼ぶ。 DICグループでは、2007年より東京大学 分子細胞生物学研究所 伊藤准教授監修のもと、日本塗料工業会、石川県工業試験場、カラーユニバーサルデザイン機構らと共同で、カラーユニバーサルデザインの考え方を体現した推奨配色セットの開発に取り組んできた。本配色セットは、塗装・印刷・画面の用途ごとに、それぞれの色材の特徴を踏まえて色を選定し、どのような色覚の場合にも共通した色名を想起しやすい色調に調整した。また、塗装の色指定で用いられる「JPMA塗料用標準色」、一般的な印刷物の色指定に用いられる「CMYK値」、画面やモニターなどの色指定に用いられる「RGB値」の3種類の色彩値を設定しているため、デザイナーなど色を扱う現場の人にとって実用性が高い。この研究開発の経緯を実際の使用例とともに紹介する。 |
||
| 第60回 | 2014/3/5 (水) |
小松 由梨果 (千葉大学 大学院 人文社会科学研究科・博士前期課程) |
| ハトにおけるKanizsa型錯視 -明るさ弁別課題・プライミングを用いた検討- | ||
|
複数の黒色パックマン型図形が中心を向いて配置され,その直線部分の輪郭同士がなめらかに連続しているとき,ヒトはそれらの図形に囲まれた領域(検査野)に物理的には存在しない輪郭を知覚し,その内部を実際より明るく知覚する.このような現象はカニッツァ型錯視と呼ばれており,心理学実験でヒトだけでなく他の動物種でもその知覚が報告されている.本研究会では,ハトもカニッツァ型錯視を知覚するか,検査野の明るさ弁別課題,視覚探索課題を用いて実験的に検討した結果を報告し,ヒトとハトの視覚特性の種差について生態学的環境の種差の視点から考察する. |
||
| 第59回 | 2014/2/12 (水) |
今泉 修 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻・博士後期課程) |
| 風景や絵画が誘発する視覚的不快 – 片頭痛患者と健常群の比較 | ||
|
片頭痛は,発作的に頭の片側が痛む慢性頭痛である。患者は視覚過敏であることが多く,例えば,高コントラストの格子模様に不快を感じやすい。著名な画家の中には片頭痛患者もおり,視覚体験が絵画に影響していた可能性も指摘されている。他方で,不快を誘発しやすい絵画は特徴的な空間周波数特性を示すことが知られているが,より具象的な刺激である風景については未検討であった。 本発表では,より具象的な視覚刺激である風景画像を解析して,不快な風景に特徴的な空間周波数特性を検討し,片頭痛患者と健常者とにおける視覚的不快の評価を試みたことを紹介する。さらに,片頭痛患者として知られるゴッホなどの絵画を画像解析することで,視覚過敏が創作物の空間周波数特性へどのように影響するかを検討したことも紹介する。 |
||
| 第58回 | 2013/12/18 (水) |
東 洋邦 (株式会社 東芝) |
| 屋内LED照明の不快グレア評価方法 | ||
|
白色LEDの発光効率の向上に伴い,LED照明器具は局所照明だけでなく全般照明にも利用されつつある.しかしLED照明器具は,発光部の輝度や面積など,既存の照明器具と異なる特徴を持つ.そのため,単に既存の照明器具をLED照明器具に置き換えただけでは,不快グレア(まぶしさ)が異なる場合がある.このような背景から現在,LED照明環境に対応した不快グレア評価方法の研究が注目されている.本講演では,現在使われている屋内照明の不快グレア評価方法(UGR法)とその問題点を解説するとともに,発表者らが行っている不快グレア評価方法に関する研究について紹介する. 本研究の成果は,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果から得られたものである. |
||
| 第57回 | 2013/11/20 (水) |
鈴木 晴翔 (千葉大学 大学院 工学研究科 建築都市科学専攻),国分 詠美子(工学部建築学科) |
| 変動照明に対する在室者の知覚に関する研究 | ||
|
オフィス等における照明エネルギー削減のための技術として在席連動の照明制御がある。これは、執務者が席を離れると人感センサーが感知してその席の照明を消灯/調光するものである。この設備の問題として、突然の変化が他の在室者の集中を妨げることが指摘されている。これに対して、ある程度の時間をかけて調光することにより在室者に知覚されにくくすることが提案されているが、そのための適切な調光速度や調光幅、作業内容や空間状況などとの関係については知見が乏しい。また、先行研究の大半は、一様なアンビエント照明のみの状態を扱っているが、これはタスクアンビエント照明やパソコンによる作業が一般化した今日のオフィス環境との乖離は否めない。このような問題意識に立ち、タスク照明・アンビエント照明の連動調光や、変動照明の知覚に及ぼす変動設定要因の検討等の本研究室の最近の取り組みを紹介する。 |
||
| 第56回 | 2013/10/23 (水) |
牛谷 智一 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| ミツバチの齢間分業と認知発達 | ||
| セイヨウミツバチ(Apis
mellifera)は,羽化後の日齢に応じて異なる役割を果たすことが知られている。一般に2 -
3週齢までは巣内の仕事に従事し,それ以降は集蜜など外勤に転じる。諸環境要因により2週齢に達するまでに外勤に転じる早熟バチが出現することがあるが,早熟バチは採餌効率が悪く,その増加が巣の崩壊要因となることがわかってきた。しかし,早熟バチと通常バチでは認知様式・認知能力に違いがあるのか,まだ知見は乏しい。研究会では,単純な色の逆転学習課題では差が見られなかった早熟バチが,空間探索課題では通常バチと異なる探索様式を示した実験について報告し,柔軟な空間探索方略のあり方について考察する。 |
||
| 第55回 | 2013/9/9 (月) |
大武 美保子 (千葉大学 大学院 工学研究科・環境健康フィールド科学センター) |
| 写真を用いた会話-共想法による認知活動支援 | ||
|
自分の体験に基づいて,考えたり感じたりしたことを語り合い聞き合う,双方向の活発な会話は,加齢と共に低下しやすい認知機能を活用することができ,機能維持につながることが期待されます.そのような会話を確実に発生するよう考案した会話支援手法,共想法と,これを病院,介護,福祉施設で実施し,得られた知見を紹介します.共想法は,(1)
あらかじめ決めたテーマに沿って参加者が話題と写真を持ち寄り,(2)
参加者全員の持ち時間を均等に決めて,話題提供する時間と質疑応答する時間に分けるという二つのルールにより定義されます.共想法の実施研究を進める研究拠点として設立したほのぼの研究所における共想法実施の様子や開発中の会話支援ロボットを動画でご覧頂くと共に,一分で一枚の写真について話題提供する一分共想法を体験頂き,今後の展開について議論したいと思います. |
||
| 第54回 | 2013/7/23 (火) |
津村 徳道 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| 質感工学とその応用 | ||
|
商品の色や質感は,商品の印象を大きく左右する重要な要素の一つである.開発段階においては,色や質感は,形状と同様に,数値的な値ではなく実際に物体を観察することでのみ評価されることが多い.形状に関しては,モックアップを作成したり,コンピュータグラフィックスにより表示したりすることにより,試作前にある程度評価は可能である.しかし,色や質感に関しては,その表示デバイス依存性,照明環境依存性や,色や質感の正確な表現技術の未成熟さ等から試作前の評価は困難であり,開発サイクルにおけるボトルネックとなっているケースが多い.したがって,商品の色や質感を予測し,人間の目に観察される画像として正確に再現することが現在求められている.本報告では,質感と工学のフレームワークを簡単に述べ,いくつかの質感にかかわる研究例を紹介する. |
||
| 第53回 | 2013/6/28 (金) |
今井 良枝 (株式会社 東芝) |
| LED照明の好ましさに基づいた演色性評価 | ||
|
LED照明は急速に普及しているが,現行の演色性評価方法ではLED照明の演色性を正しく評価できないとの指摘もある.CIE(国際照明委員会)では,忠実性以外の演色性評価手法について検討する技術委員会TC1-91を2012年9月にスタートさせた.本研究では,実環境に近く照明に十分に順応した状況を想定し,分光分布を様々に変化させたLED照明下の照明視環境で,被照射物の色の見えを視感評価実験するための大型LED
照明装置を試作し,評価用システムを構築した.このシステムを用いた色の見えに関する感性的な主観評価実験の結果から,各種照明の色の見えにおいて好ましさ評価は,Ra
との相関関係よりも鮮やかさ評価と相関関係が強いことが示唆された.現在,好ましさと鮮やかさとの関係を明確にするために,照明下での評価対象物の測色的変化と好ましさとの関連性について,検討を続けているので紹介する.本研究の成果は,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託業務の結果得られたものである.
|
||
| 第53回 | 2013/6/6 (木) |
佐久間 直人 (千葉大学 大学院・博士後期課程) |
| 複数同時に呈示された数字の高速処理に寄与する諸要因の検討 | ||
|
類似した刺激を複数同時に観察したとき、個々の刺激に関する情報の処理が困難であっても、全体の情報に関する統計的な特徴が瞬時に抽出される。例えば、円の大きさやパッチの傾きの平均が瞬時に獲得されることが示されている(e.g.
Chong & Treisman,
2003)。アラビア数字の持つ意味(大きさ)もこの統計的特徴の一つのように作用すると報告されている。複数の数字から構成されている視覚刺激配列を2つ並べて瞬間呈示すると、配列内の数字の平均値が大きい方や、ターゲットとして指定した数字が多く含まれている方を速く正確に指摘することができる(Corbett
et al.,
2006)。しかし、この現象の基礎となるメカニズムには未だ不明な点が多い。本研究では、この現象が本当に“数字の意味が図形のように処理される”ために生じるのかを検討した。実験1~3では、この現象がアラビア数字という刺激の物理的な特性に依存して生じているわけではないことと、概念的な意味付けによる処理が関与していることを示した。実験4~6では日本語表記の特性を利用して、表意文字であり、量的な意味を有し、使用頻度が非常に高いという数字の特異な性質を要因として操作し、高速処理は高頻度で使用される有意味記号の処理特性であることを示した。試み的な実験ではあるが、単語や文字の効率的な認知能力に関する研究や、一度に複数の刺激を処理する機能に関する研究への貢献が期待される。 |
||
| 第51回 | 2013/4/25 (木) |
黒岩 眞吾 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| 人と機械の音声言語処理 | ||
|
現在の音声認識技術は,人と同様にトップダウン処理とボトムアップ処理を巧みに組み合わせる事で実現されています.本日の発表では,人が脳梗塞等により言葉の理解や生成が困難となる症状である「失語症」を解説するとともに,機械による音声言語処理を人の音声言語処理と比較しながら解説を行って行きます.また,音に関する錯覚現象やそれを利用した雑音除去手法についても紹介します.最後に「失語症」の方向けに現在開発中の言語訓練・支援ツール(音声認識,自然言語処理を利用,今後,画像処理を使いたい)のデモンストレーションを行い.今後の方向性について皆さんと議論できればと思っています.
なお,発表者の専門である機械による話者照合技術では,応用分野の性質上ボトムアップでの処理が中心になります.個人の音声が1日の中で,そして季節や加齢でどのように変化して行くか,やや気の長い取り組みとして,週1回,朝昼晩10分間,10年にわたり音声の録音を続けています.時間が許せばこのデータを用いたいくつかの知見も紹介したいと思います.
|
||
| 第50回 | 2013/3/21 (木) |
桑山 哲郎 (千葉大学 工学部 画像科学科非常勤講師 / キヤノン) |
| 「画像技術史」の授業と錯視の関係-伝えたいことと生徒の興味との食い違い | ||
|
1987年に工学部画像工学科(当時)で「画像技術史」の講義を非常勤講師として担当し,現在までずっと続けさせていただいている。 この講義では,画像機器の成り立ちの全体像を「技術史」という視点を用いて把握させる事を狙いとしている。ところが教える側の想いとは多少食い違い,生徒の興味が「錯視」的な部分に集中し過ぎることが多少悩みとなっている。講義を通じて見えてきた課題を紹介する。 この講義では,画像を構成する5つの要素について,実物を見ている状態と,画像機器により再現される感覚を対比している。5つの要素として (1)大きさ・形 (2)奥行き (3)動き (4)色 (5)明暗 を取り上げているが,これはルネサンス以来の絵画の教育で取り上げている要素とほぼ重なっている。実物を見ているとき,いろいろな物理的な手がかりから再構成することでそれぞれの要素が得られるが,同様な手がかりを作り出すことで画像機器が成立していると考える。工学技術として画像機器は極めて「当たり前」の事を行っているので,特にわざわざ「錯視」や「だまし」と言い立てる必要も無いように思えるのだが,講義の感想を書かせると刺激の強いものに興味が集中していることが分かる。いろいろなの実例を紹介する。 |
||
| 第49回 | 2013/2/21 (木) |
井上 はるか (千葉大学 大学院 人文社会科学研究科・博士前期課程) |
| 顔画像の動的特性が表情の認知過程に及ぼす影響 ―評定尺度法と心理物理学的測定法による検討― | ||
|
変化する表情を観察する際,最終的な表情の認知処理が変化方向へシフトする現象が報告されている(伊師・行場, 2006; Jellema et
al., 2011; Yoshikawa & Sato, 2008)。本研究では,この動的表情観察における表情のシフトの特性を調べることで,表情の動的認知処理過程について検討した。 形容詞対を用いた評定尺度法による実験では,表情のシフトは消失方向(表情顔から無表情へ弱まる変化)や最終表情が中程度になる場合に顕著であり,表情や他の条件によりシフトが大きくなる速度が異なった。さらに,異なる表情間の変化ではシフトが生じるものの,異なる性別間の変化では生じなかったことから,社会的文脈を参照した解釈的な処理が表情のシフトの基礎にある可能性が示唆された。 恒常法により標準刺激(動画像)と比較刺激(静止画像)を継時提示して2AFCを行った実験では,表情のシフトは表出方向(無表情から表情が強まる方向)のみで生じ,倒立提示の影響を受けなかった。さらに,標準刺激と比較刺激とで異なる人物の顔画像を提示した場合でも同様の傾向が認められたことから,恒常法的手続きにおいても表情としての処理がなされていたことが確認された。これらの結果から,動的表情観察における表情のシフトに,表情の形態的な処理が関与しており,表情変化の分かりやすさに応じて先を予測するような処理が関与している可能性が示唆された。 動的な表情の認知には多面的な処理側面があり,各々の処理段階において独自の方略により動的情報を処理しているものと考えられる。このような動的処理の過程は,表情認知において,適応的な認知の成立に寄与しているものと考えられる。 |
||
| 第48回 | 2012/12/20 (木) |
鈴木 卓治 (国立歴史民俗博物館/千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| ある2型3色覚者の単波長光の色の見え方に関する事例報告 | ||
|
いわゆる色覚の多様性(polymorphism)の問題について,2色覚についての研究は古くより行われよく知られていますが,いわゆる異常3色覚について扱った研究はあまり多くありません. 本発表では,急速に普及が進むLED式信号機について,ある2型3色覚者(被験者ST)の色の見え方について報告します.LED式信号機の黄色信号灯は主波長が約590nmの,単波長光に近い単峰型の分光分布をもちます.正常色覚者には,黄色灯の黄色はややオレンジがかった黄色(マンセル色相で5YR付近)に見えていますが,被験者STには,わずかに緑かかった黄色(マンセル色相で5Y付近)に見えます. 本報告では,赤色LED光と緑色LED光の輝度を変えて黄色LED光にマッチングさせ,それらの光がどのマンセル色相に見えるかを標準色票との比較により比定する実験について紹介します.マッチング実験に使用した治具をもちこんで,参加者に実験を体験していただきたいと考えています. またプログラマブル光源を利用して,単波長光の色相の見え方を正常色覚者と被験者STで比較した実験についてあわせてご紹介します. 本発表は2005年と2009年に日本色彩学会全国大会で発表した内容を再構成したものです. |
||
| 第47回 | 2012/11/28 (水) |
山口 秀樹 (独立行政法人 建築研究所) |
| 視野の色彩分布と空間の明るさ感 | ||
|
建築空間において,空間の明るさ評価指標には照度を用いることが一般的であるが,照度だけでは明るさの感覚と矛盾するケースも多く存在する.この問題に対して,最近の研究では視野の輝度分布に着目して評価をする方法がいくつか提案されている.これらの研究により人間の感覚によく一致する明るさ評価指標が構築されつつあるが,視野の色情報も加味した指標はできていない.本研究では空間の明るさ感を複数の心理評価方法で評価するとともに,視野の輝度・色度分布を計測することで,明るさ感と測光量の関係について検討した. |
||
| 第46回 | 2012/10/31 (水) |
草野 勉 (東京海洋大学 大学院 海洋科学技術研究科) |
| 観察時の頭部位置および背景の傾きによる両眼視方向の偏位 | ||
|
ウェルズ―ヘリングの視方向法則によれば、単一視が成立している両眼刺激の知覚される視方向は、左右眼における視軸からの偏位の平均となる。発表では、視方向知覚が、この両眼視方向法則から予測できない事態を紹介する。特に、頭部位置の変化および背景刺激の傾きが相対視方向の偏位をもたらすことを示した実験結果を、デモンストレーションを交えて提示する。続いて、この偏位の要因について、cyclovergenceや背景・枠の効果を検討するために実施した実験について紹介しつつ、参加者の皆様と議論ができればと考えている。
|
||
| 第45回 | 2012/8/27 (月) |
山本 昇志 (東京都立産業技術高等専門学校 情報通信コース) |
| HDR画像のトーンマッピングと評価方法 | ||
|
照明された物体に発生する光沢は表面性状だけでなく,形状や位置の手がかりとして重要である.これらを正確に再現するためには対象物体の三次元表示だけでなく,鏡面反射成分である光沢にも三次元的な奥行き情報を与える必要がある.このことはBlake(1990)らによって初めて形式化され,多くの研究者がその奥行き情報の有益性を論じてきている.ただ,立体的な再現の効果を定量化するためには「Panumの融合域」と呼ばれる知覚的な感覚融像や,輻輳・調節運動といった初期視覚との関連を明確にしなければならない.そこで本発表では我々が今まで行った初期視覚に関する定量化手法と,光沢に立体再現を適用した際の評価結果について紹介するとともに,その効果について議論させて頂く. |
||
| 第44回 | 2012/7/26 (木) |
堀内 隆彦 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| HDR画像のトーンマッピングと評価方法 | ||
|
高いダイナミックレンジからなる自然シーンを獲得するために,実シーンをHDR画像として計測することが一般的になりつつある.一方において,一般の出力デバイスでは,依然としてLDR画像として再現することが主流であるため,画像再現過程においてHDRからLDRへダイナミックレンジを圧縮するためのトーンマッピング技術が不可欠となる.このとき,視覚系は非線形であるため,適切なLDR再現画像を得るためには,視覚系を考慮した非線形なトーンマッピング技術が必要となる.本講演では,我々が提案している網膜の応答関数を空間的に可変としたトーンマッピング法を紹介し,長年にわたって画質改善法として利用されてきたRetinexとの関連性を述べる.また,トーンマッピングされた画像の客観的な評価法の確立を目指して行った,基礎的な心理物理実験データについて紹介する. |
||
| 第43回 | 2012/6/27 (水) |
桂 重仁 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 木材画像の質感に影響を与える要素 ~色と空間周波数からの検討~ | ||
|
私たちの身の回りには多くの木材製品が存在している.木材には様々な種類が存在し,それらの色や模様は暖かみや豪華さといった印象を与えることが知られている.また,日本では家屋に木材が多く使用されているため,木材への嗜好性が強く需要が大きいと言える.しかし,天然木材の木材製品への利用は,製品の均一性の管理,高コスト,環境負荷といった面において大量生産という点から障害が多い.したがって,天然木材の代替品となる製品の需要はますます大きくなると考えられる. そこで,本研究では木材を試料とし画像化した木質感に着目した.試料の凹凸や照明の影響を排し,2次元情報のみを用いた場合により自然な木質感に影響を与える要素を検討した.色情報に注目した場合,明度情報が最も質感に影響を与えていることが示唆された.また,空間周波数に注目し,自然なパワースペクトルの形状や平均明度との関係を検討中であり,途中ではあるが結果を報告する. |
||
| 第42回 | 2012/5/23 (水) |
和田 有史 (独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構) |
| 食品の質感視知覚 | ||
| 食品は味覚・嗅覚だけでなく、すべての感覚器官からの情報によって知覚
されている。(独)農研機構食品総合研究所食認知科学ユニットの心 理・行動
科学グループは、そのような多チャンネル情報による食品認知にアプローチして いる。その中でも本発表では、食品の認知における質感視知覚 に関する心理物
理学的研究を紹介する。鮮度に関しては知覚される鮮度と輝度分布の関連につい て、柔らかさの知覚に関しては同一物体として知覚され る視覚刺激に含まれる
運動の位相差が知覚に与える影響について発表する。 |
||
| 第41回 | 2012/4/26 (木) |
戸部 和希 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士前期課程修了) |
| 白色LED光源の演色性と照明空間の印象の評価 | ||
|
LED光源は従来の光源(蛍光ランプ等)と発光原理が異なるため,分光エネルギー分布も今までにはない形をしている.このため,LED光源の演色性も従来のものとは異なり,照明空間の視覚的印象にも異なった影響を及ぼすことが分かっている. LED光源の演色性を評価する際,従来の演色性評価方法がそのまま適用できるかどうかが問題になっており,CIE TC1-69において新たな演色性評価方法が検討されている.これらの演色性評価方法においては,適用する色順応モデルと色差を求める際の色空間の選択が重要である.本研究では被験者実験により,LED光源下の実験刺激の対応色を参照光源下において求める.それら対応色に関してCIELAB,CAM02-UCSの各色空間で評価を行い,LED光源による色の見えの特徴を明らかにする. またLED光源を用いた照明空間の印象に関して,本研究では室内を模したミニチュアを用いた照明空間の評価実験を行う.評価にはSD法を用い,因子分析により照明空間の評価に影響する要素を抽出し,各LED光源が照明空間の印象に及ぼす影響の特徴を明らかにする.実験結果より,LED光源は参照光源とは異なる色の見えと照明空間の印象を与えた.これにより,照明による色の見えの変化は,照明空間の印象にも関係していることが示唆された. |
||
| 第40回 | 2012/3/28 (水) |
後藤 雅宣 (千葉大学 教育学部造形教育講座) |
| 構成学に関する研究紹介 | ||
|
教育学部には、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に展開されるすべての教科領域に関わる研究分野が存在する。その中で図画工作・美術・芸術美術を担当するのが造形教育講座である。 音楽とともに表現教科と呼ばれ、そのための理論と実技の両輪を担う。視覚芸術を扱う領域であることから、視覚・視知覚の原理や特性の活用に関して、表現そのものをもって実証するといった研究スタイルも同時に求められている。実技表現の成果をも評価対象とされるきわめて特異な世界である。 また、それらをどのように教育活動に生かしうるかというテーマが、いま一つの柱となる。造形教育講座の中では、いわゆる絵画や彫刻、工芸、といった分野の他に、「構成」という分野が存在する。Gestaltという言葉に由来し、絵画や彫刻、デザインや工芸といった歴史の中で確立されてきた表現世界に通底する、美術の基礎を研究・教育する世界である。今回は、個別的な研究ではなく、その状況や背景を紹介しながら、教育制度の中での色や形の問題の取り扱いや、美術界と造形教育との関係などについて、ともに考えたい。 当日は作品現物も見ていただく予定であり、美術館での作品鑑賞のようなお気軽な気分でご参加いただければ幸いである。 |
||
| 第39回 | 2012/2/9 (木) |
大北 碧 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| ハトにおけるカテゴリ探索の検討 -顔合成画像を用いて- | ||
|
複雑な背景の中から, 様々な餌や様々な天敵などのカテゴリを効率よく探索することは,
ヒトを含めた動物が環境に適応するために必須な注意機能だと考えられる。本研究では妨害刺激である非カテゴリ事例の中から標的刺激であるカテゴリ事例を探索するカテゴリ探索課題を,
多くのカテゴリ化研究や視覚探索研究で被験体として用いられてきたハトに行った。標的刺激であるカテゴリ事例は,
日本人男子学生顔画像の合成画を用いて作成した。自然カテゴリの事例を模しており,カテゴリの事例が共通して持つ要素と事例に特異的な要素をもつ。妨害刺激にはカテゴリ作成に用いなかった顔画像を用いた。 |
||
| 第38回 | 2011/12/22 (木) |
岩坂 正和 (千葉大学 大学院 工学研究科) |
| 生物磁気の最近の話題 | ||
|
電磁場の生体作用,あるいは生物が電磁場をどのように感じるかについて,物質レベルから生物個体レベルまでのスケールにおける研究を紹介します.ここでは主に直流磁場の生体物質レベルでの効果の例を取り上げ,そのメカニズムの考え方を述べたいと思います.光や視覚に関する話題として,魚のうろこに存在する高屈折率のフォトニック結晶の光散乱や構造色における磁場効果を紹介致します.また,近年話題となっている鳥の視覚系における光感覚機構に重畳した磁気知覚の存在(他の研究者の情報)も解説し,磁気の生物効果の現状を議論致します. |
||
| 第37回 | 2011/11/24 (木) |
木村 敦 (東京電機大学 情報環境学部),増田知尋,和田有史 ((独)農研機構・食品総合研究所) |
| ブランドロゴの記憶色 | ||
|
熟知物の色のみえには記憶色が影響を及ぼすことが知られている. たとえば, Hansen et al. (2006) は,
見慣れた野菜の画像の色度を灰色に見えるまで調整させる課題を行い,
その主観的灰色点が灰色よりも典型色の反対色側にずれること (記憶色効果) を示した. 記憶色効果は対象を熟知していることによって生じる可能性が高いが,
Hansen et al. では熟知物のみを用いていたため, 記憶色効果の強さが熟知度の関数として記述されるかどうかは未検討である. そこで本研究では,
熟知度 (主観的な接触頻度: 高, 中, 低) の異なる食品関連企業のロゴマークをターゲットとし, 対象の熟知度と記憶色効果の関係を検討した.
本講演では, 筆者らが行った上記の実験研究について紹介する. |
||
| 第36回 | 2011/10/13 (木) |
兼松 えりか (株式会社 ニコン) |
| 色になじみのある物体による色の見えへの影響 | ||
|
色が特徴的な物体そのものの色の見えについては幾つか研究報告があり、特徴的な色の方向へシフトする(例えばバナナであれば、無彩色が黄色にシフトして見える)という報告がある。しかし色が特徴的な物体による色の見えへの間接的な影響は研究報告が余りない。一方、画像処理技術の分野では、特定の被写体の色をWBのゲイン算出に利用する手法も提案 |
||
| 第35回 | 2011/9/26 (月) |
今泉 祥子 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| ハッシュ関数に基づくコンテンツ保護技術 | ||
|
コンピュータの性能向上,ネットワークの広帯域化により,ディジタルコンテンツの扱いが容易となってきた.これに伴い,商品としてのディジタルコンテンツの流通が増加しており,その著作権保護が問題となっている.これらコンテツ保護に対する代表的な対策技術の一つに,電子透かしがある.電子透かしは,コンテンツに著作権情報を埋めることにより,不正利用を抑止する方式である. |
||
| 第34回 | 2011/7/28 (木) |
澤山 正貴 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 輝度エッジの解釈過程における肌理とエッジの処理の相互作用 ―肌理上の水染み現象を用いた検討 | ||
|
ある面で反射された光が眼に届く時の強度(輝度)は、その面に当たる照明の強度によっても、面の反射率によっても変化する。そのため、同一の輝度を生み出す照明強度と反射率の組み合わせは無限にあり、単一の輝度から照明強度と反射率を一義的に決めることはできない。この多義性を解くために、視覚システムは輝度の変化する領域(エッジ)を解析し、輝度エッジが照明の変化によるものか反射率の変化によるものかを解釈しなければならない。一般に、輝度エッジのぼけや、エッジ間の肌理の連続性は、そのエッジを照明エッジと解釈する手がかりとなることが知られている。しかし、肌理上にぼけた輝度エッジをもつ領域を配置すると、単独であれば照明エッジの解釈を促進する手がかりを組み合わせているにもかかわらず、水が染みたような反射率の異なるものとして知覚されることをわれわれは発見した
(肌理上の水染み現象, 澤山・木村2011)。本発表では、この現象生起の基礎となるメカニズムについて検討した研究を紹介する。 |
||
| 第33回 | 2011/6/23 (木) |
矢田 紀子 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| 色覚特性のニューラルネットワークモデル | ||
|
さまざまな照明条件で撮影された画像中の色認識はコンピュータビジョンやマシンビジョンに有効であり非常に重要であるが,色恒常性を解決する手法は未だに確立されておらず,特に,人間の色覚特性を調べた心理物理実験の結果を利用した有効な色認識手法は提案されていない. |
||
| 第32回 | 2011/6/2 (木) |
高橋 良香 (千葉大学 大学院 工学研究科) |
| 視物質メラノプシンを含む網膜神経節細胞が関与する非視覚的作用メカニズムの推定 | ||
|
鳥類や爬虫類、両生類、魚類では、生体リズムへの光入力となる専用の光感受性細胞が脳の基底部や松果体にあることが知られており、哺乳類においても同様の光受容物質があることが近年(2002年)、発見された。哺乳類では、この視物質が網膜の神経節細胞にあり、生体リズムへの光入力や瞳孔反射に寄与することが報告されている。そこで、本報告では、この視物質が作用する反応に着目し、その作用を明らかにすることを研究目的とした。 1つ目の研究では、光が生体リズムに与える影響の程度を表すと考えられている「メラトニン(夜間に分泌されるホルモンの一種)の光による分泌抑制作用」を定量化することで、そのメカニズムを推定した。光曝露によるメラトニン分泌抑制作用に関する実験では、散瞳薬が使われることが多く、瞳孔対光反射(PLR)が起きない状態で実験が行われている。そのため、ここでは、PLR による網膜への到達光量変化の効果を考慮した。PLR を考慮したモデルと実際の実験結果を比較したところ、光曝露によるメラトニン分泌抑制作用を十分に推定することができなかった。十分な推定ができなかった理由として、光源の分光分布特性によって、メカニズムが変化することが予想された。 2つ目の研究では、ノックアウトマウスを使った既往研究から、高放射量曝露時のPLR にこの視物質が寄与するという仮説を立て、その仮説を確かめる実験を行った。実験では、2つの単色光を使い、プルキンエ現象の知見を応用して、杆体からこの視物質への分光感度変化が起こるかを確かめた。2つの単色光の感度差から分光感度を推定したところ、仮説通りの結果が得られた。 |
||
| 第31回 | 2011/4/7 (木) |
眞鍋 佳嗣 (千葉大学 大学院 融合科学研究科) |
| Virtual or Real ? 複合現実感技術 | ||
| 複合現実感(Mixed
Reality)とは、現実世界にコンピュータで生成された情報を重ね合わせて提示するものである。関連する分野として、Virtual
Reality、Augmented Reality、Augmented Virtualityがあるが、Mixed Realityはこれらを包含する概念となっている。 視覚(映像)における複合現実感においては、現実環境と仮想環境(物体)を違和感なく重ね合わせるために、時間的整合性、幾何学的整合性、および光学的整合性が必要となる。これら3つの整合性を保つために、鏡面球と二次元マーカを組み合わせた3Dマーカを用いた手法をこれまでに提案してきた。本発表では、複合現実感技術についての解説ならびに3Dマーカを用いた現実環境と仮想物体の違和感のない重ね合わせ手法について紹介する。 |
||
| 第30回 | 2011/3/3 (木) |
相田 紗織 (東京海洋大学 大学院) |
| 両眼視差に基づく見かけの奥行き:逆二乗法則からの逸脱 | ||
|
両眼立体視において、観察距離、両眼視差が同じで視差勾配が類似していれば、見かけの奥行き量が同じであることは自明の理として受け入れられている。しかしながらわれわれは、2面または3面の重なり合った面を作り出す立体透明視刺激において、被験者に最も近い面と最も遠い面の間の両眼視差が同じでも3面刺激の見えの奥行き量は、2面刺激のそれよりも小さいという現象を見出した。立体透明視刺激はRDSで作成した。本研究では2つの面をシミュレートした立体透明視刺激を2面刺激、3つの面をシミュレートした立体視透明刺激を3面刺激と呼んだ。 われわれはこの現象を確認するために4つの実験を行った。実験1では、重なり合った面(2面と3面)の間の奥行き量を再生法で測定した。実験2では、3面刺激の両眼視差と同じ奥行き量を生む2面刺激の両眼視差を求めた。これらの実験の結果、2面刺激と3面刺激の両眼視差が同じでも、3面刺激の外側の2つの面間の知覚された奥行き量より2面刺激の知覚された奥行き量が大きくなる場合があることがわかった。さらに、実験3と4ではそれぞれドット密度、刺激の大きさ(視野の大きさ)を操作し、見かけの奥行き量を測定した。その結果、実験3ではドット密度に関係なく現象が観察された。実験4では刺激が比較的大きく両眼視差が比較的大きい場合に現象が観察された。また、大きい刺激の知覚される奥行き量が小さい刺激の知覚される奥行き量よりも大きく知覚された。われわれはこれらの結果を大域的立体視という枠組みで説明したい。 |
||
| 第29回 | 2011/2/10 (木) |
喜多 靖 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程/スタンレー電気 研究開発センター) |
| HIDと白色LEDにおける光源色の見えと測色値の不一致 | ||
|
一般的に測色学の分野では,等色関数を用いて色度値を算出し,色を定量化することが行われている.当然のことであるが,分光分布が異なっていても,三刺激値が同じであれば等色する.これを条件等色と言い,条件等色対を観察すれば,同じ色として知覚される. しかしながら,HID(放電灯)と白色LEDからなる条件等色対を観察すると,異なる色として知覚された.色の見えと測色値の不一致は,照明灯具の品質や商品性に影響を及ぼすことが考えられ,光色の決定に関しては重要な項目である. そこで我々は,光源の色の見えを調査するために,HIDと白色LEDをそれぞれ参照光源とし,R,G,BLEDをマッチング刺激として等色実験を行った.結果,参照光源が白色LEDの場合,等色点は,参照光源の色度値近傍に分布した.一方,参照光源がHIDの場合,等色点は,参照光源の色度値よりも約700K高色温度側に分布した. 更に,この光源色の見えと測色値の不一致の原因を探るため,導出方法が異なる等色関数を用いて色シフトの計算を行ったので,その結果について報告する. |
||
| 第28回 | 2010/12/9 (木) |
谷口 昌志 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士前期課程) |
| 記憶質感と好ましい粒状性について -ノイズのタイプを考慮して- | ||
|
デジタル画像にノイズを付加すると,その画像に対する好ましさが向上する絵柄があることが知られている.本研究では,ノイズ付加による好ましさの向上の理由として「記憶質感」を提唱し,記憶質感の持つ性質を探ることを目的としている.「記憶質感」とは我々が物体を思い浮かべた時にその物がもつ質感のことである.人が物体を見た時に実際に感じる質感と,記憶における質感をホワイトノイズを付加・除去したサンプル画像を用いて主観評価により調査し,どのような違いがあるかを検討した.その結果,記憶質感は対象物の質感に依存して変化し,その変化は対象物自身の持つ質感を打ち消すように記憶では粒状感を増加・減少する性質を持つことがわかった.また,記憶質感と画像の好ましさの関係についても調査を行ったところ,記憶質感と好ましさの間には相関が見られ,記憶の質感に近い画像ほど好ましいと感じられる事がわかった.これらのことは,「記憶質感」に基づき付加するノイズの粒状性を調整することにより,好ましい画像の再現が実現できることを示唆している..
|
||
| 第27回 | 2010/11/4 (木) |
川本 一彦 (千葉大学 大学院 融合科学研究科 情報科学専攻) |
| 粒子フィルタに基づく動画像解析 | ||
|
粒子フィルタは,この10年で目覚しく発展している新しい時系列解析の方法として,さまざまな分野で用いられている.とくに,非線形・非ガウス型時系列モデルに対して威力を発揮する.対象が線形・ガウス型モデルならば,カルマンフィルタで十分相手が務まる.非線形モデルであっても,線形近似で我慢できるなら,拡張カルマンフィルタでなんとかなる.これでもだめなとき,粒子フィルタの出番である.解析的に扱えない手ごわい相手であっても,強力な計算資源を武器に,モンテカルロ法を駆使して,数値的に接近していくところにその力の源泉がある.本講演では,粒子フィルタの活発な応用分野の一つであるコンピュータビジョンにおける物体追跡の話題からはじめ,さらにそれに基づくいくつかの応用事例について筆者の研究を中心に紹介する.
|
||
| 第26回 | 2010/10/14 (木) |
吉澤 陽介 (千葉大学 大学院 工学研究科人工システム科学専攻) |
| 色空間における慣用色名認識の定量化の試み ~JIS Z 8102「物体色の色名」における慣用色名について~ | ||
|
普段、何気なく無意識に用いられている慣用色名であるが、その慣用色名の用いられ方を振り返ってみると、誤認がなされていたりなど必ずしも正しいとは限らない。また、あまり用いられない慣用色名も存在し、死語になりつつある色名も存在する可能性がある。その事実は、先行研究においても言及されている。 もしも誤認されていたり、知られていない色名が多ければ、日本の歴史の一部を失うことにも繋がるかもしれない。特に、JIS Z 8102「物体色の色名」に採録されている慣用色名の在り方とともに真価が問われる。 本研究は、JIS Z 8102に採録されている慣用色名がどの程度認識されているかを把握する為に色名マッチングタスクを実施し、調査紙によるアンケート調査を基にして考察を行った。 一連の考察を踏まえて、如何にして慣用色を正確に用いて伝達を行っていくか、そして慣用色の由来となる対象が有する色域、素材、テクスチャなどの「不変的側面」、およびJIS の代表値や色票を基にして工業製品やメディアなどに用いるといった「使用的側面」の両立を如何にして図れば良いかを検討するきっかけとなり得る。 |
||
| 第25回 | 2010/9/9 (木) |
一川 誠 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| 両眼視差量が画像の印象におよぼす効果 | ||
|
両眼視差手がかりの大きさと知覚される奥行量,感性的判断の関係について調べた一連の実験結果を紹介する.各実験では,交差視差,非交差視差それぞれ0~70分程度の大きさの両眼視差を示すステレオグラムを20名程度の観察者に提示した.単純な構造の線画ステレオグラムの観察では,美感や快適感を含む評価性の印象は10~20分の両眼視差で最も強くなった.活動感は両眼視差量や見かけの奥行量に対応して増大し,重さなどを含む力量性の印象は,交差視差で弱くなることが認められた.様々な印象を喚起する具象的画像のステレオグラム観察では,視差量が大きくなるほど評価性の印象,活動感,現実感が強められた.また,画像の具象性に関わらず,多層構造にすることで見かけの奥行が大きくなること,大きな視差量ほど評価性の印象,活動感,現実感を強めることが認められた.以上の実験結果に基づき,両眼視差を用いた映像の印象操作方法を提案する. |
||
| 第24回 | 2010/8/5 (木) |
小山 慎一 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻) |
| 視覚の臨床神経心理学:患者から学ぶ視覚の仕組み | ||
|
筆者らの研究グループでは後頭葉損傷患者の視覚障害を研究する一方で、片頭痛やてんかん患者における視覚症状および光過敏性についても研究している。一方は視覚機能の低下から起こる症状であり、もう一方は視覚機能の異常な亢進によって発症すると考えられている。これらの臨床研究と脳機能イメージング研究を比較・検討することによって視覚機能の低下、亢進、および正常な視覚の状態を多角的に検討することが可能になる。本講演では筆者らが最近行ったいくつかの臨床研究を紹介する。 |
||
| 第23回 | 2010/7/1 (木) |
平井 経太 (千葉大学 大学院 融合科学研究科 情報科学専攻・知能情報コース) |
| 空間速度コントラスト感度関数の測定・モデル化と動画像評価への応用 | ||
| 視覚系の空間周波特性は視覚系のMTF(Modulation Transfer
Function)であるコントラスト感度関数(Contrast
Sensitivity Function,CSF)で表現することが多い.CSFは輝度または色度を正弦波状に変化させた縞を提示刺激とし,その正弦波パターン(正弦波グレーティング)
が知覚できるコントラスト閾値によって決定される.また,CSFは一般に空間軸で考えられることが多いが,時間周波数を変化させることによって大きく変化することも知られている. このようにCSFはこれまで空間軸または時間軸で考えられてきたが,近年,視線が動いている刺激を追従した状態でのCSFである空間速度コントラスト感度関数(Spatio-Velocity CSF,SV-CSF)が注目されている. そこで本講演では,SV-CSFに関する研究の背景,測定,モデル化について述べる.また,SV-CSFの工学的応用例としてSV-CSFを用いた動画像の画質評価手法を紹介する. |
||
| 第22回 | 2010/5/19 (水) |
池田 光男 (立命館大学、チュラロンコーン大学(タイ)) |
| 空間認識、そして色の見え | ||
|
池田が提案した色の見えのメカニズム、照明認識視空間の概念による実験を紹介する。人がある空間に入るとまず空間の存在を認識し、ついでそこにある照明がどのようなものであるかを理解する。これが照明認識視空間である。人はその照明に適応し、白と認識する照明認識視空間の認識軸は照明の色に引きずられてその方へ回転する。照明の色によってそこにある物体の物理的な色は全て照明の色の方向へ移動する。しかし認識軸も同じように移動するから、認識軸と物理的な色との相対関係には変化が生じない。したがっているも物体本来の色が見える。これが色の恒常性である。先ず最初に、空間の認識があるというのがこの概念の基本的考え方である。空間の認識、そして色の見え、である。このことを証明する2つの実験を紹介する。 部屋を二つ作る。被験者室と壁の向こうのテスト室である。壁には大きさを変えられる四角の窓があり、ここを通して被験者はテスト室に置かれたテスト色票の色をエレメンタリーカラーネーミングで判定する。窓が小さいとテスト色票だけしか見えず、その色は被験者室に対して形成されている照明認識視空間の認識軸に照らして判定される。たとえば被験者室が赤色で照明されていると認識軸は赤色の方向へ移動している。テスト色票が無彩色だと赤色と反対方向の緑色に認識される。窓の大きさを大きくしていき、向こうに別の空間があることが分かれば、テスト室に対しても照明認識視空間が形成され、テスト色票の色はテスト室の照明認識視空間の認識軸に照らして判定される。テスト色票が無彩色ならその本来の無彩色として判定される。これが予測である。これが起きることを実験で示す。 つぎに、テスト室の装飾をほとんど赤とした場合とほとんど緑にした場合について上記と同じ実験を行う。もし色の見えが網膜上での色順応で決まってくるなら、赤の場合は赤への順応がおき、無彩色のテスト色票は緑に見えるはずであり、逆に緑に装飾した場合はテスト色票は赤に見えるはずである。これに対して照明認識視空間の概念では、空間の認識、そしてその空間の照明の認識に基づいて色が見えるとするので、テスト室の装飾の色に左右されることなく本来の色が見えるはずである。このことを実験で示す。 |
||
| 第22回 | 2010/5/19 (水) |
Janprapa Poungsuwan (チュラロンコーン大学(タイ)) |
| 写真の中にも色の恒常性 (Color constancy demonstrated in a photograph) | ||
|
照明の色に関わりなく、物体の色は白は白というように物体本来の色を見るというのが色の恒常性である。しかし写真の中に写っている物体の色は照明の色をそのまま反映して、たとえば照明が電球色であるなら、写真の中の白い物体はややオレンジがかって見えてしまう。色の恒常性は成り立っていない。 池田は照明認識視空間という概念を導入している。その概念は物体の色の見えcolor appearanceはそれが置かれた空間の照明の認識を基に知覚されるというもので、その順序は、まず空間の認識があり、照明の認識があり、照明への適応がなされ、その空間で白と見る照明認識視空間の認識軸の方向が照明の色に近づいたところに回転し、その空間の中の物体の色は認識軸からの距離(角度)によって決まってくる。白い物体は電球によって照明されると物理的には少しオレンジ色になるが、認識軸もオレンジ色のところに移動しているから、やはり白い色として見る。 写真の場合はどうか。電球色で撮影した景色の中の白い物体は物理的には少しオレンジ色に写っている。これを白色で照明された空間に置いて見る。写真はその空間の中の一物体に過ぎないから、写真の中のオレンジ色がかった白い物体はそのまま少しオレンジ色に見えるだけである。色の恒常性は写真の中の景色には起きてこない。 しかし写真の中にでも色の恒常性の成り立つ可能性が照明認識視空間の概念からはある。色の恒常性は空間認識から始まるのであるから、写真の中の景色を空間認識するようにすればよい、ということになる。もし写真の景色が立体的に見えるならその中の物体には色の恒常性が成り立つと予測できるのである。 では写真を立体的に見るにはどうすればよいか。それには視覚系が空間を立体的に見るメカニズムを利用すればよい。我々が外の3次元の景色を見るときその網膜像は2次元に次元が落ちている。でも我々は3次元空間を認識する。つまり網膜の2次元像は大脳で3次元に次元アップされるのである。写真を見る。その網膜像も2次元である。だからそれが大脳で3次元に次元アップされる可能性はある。ただし、写真の景色以外の情報がそこにあってはいけない。部屋の中で写真を見ているときは写真の他に部屋の網膜像がある。部屋は3次元であるから次元アップの機能は部屋のために使われて、写真には使われない。写真は2次元のままに認識される。だから部屋の情報を大脳に入れないようにするとより。そこで次元アップビューワー(D-up viewer)なるものを作り、写真だけが見えるようにする。するとそこには3時限空間が見え、したがってその中の物体の色には色の恒常性が働き、白い物体は白い物体として見えるはずである。このことを実証する。 |
||
| 第21回 | 2010/4/22 (木) |
中村 哲之 (千葉大学 文学部、日本学術振興会) |
| 錯視に関する比較認知研究 | ||
|
動物でも錯視は生じているのか?―こうした問いに対する研究は、古くは1920年代頃からおこなわれてきたが、さまざまな動物種で錯視の生起やその量を測定する行動的手法が十分に確立されていなかったこともあり、その多くは単一種に対して単一の錯視図形をテストする散発的な研究に限られていた。さらにそのほとんどが、「ヒトと同じ錯視が動物でも生じるか」を調べることに終始し、ヒトと異なる結果に対しては、実験条件の不備などとして扱われることもあった。しかし、錯視研究によって、ヒトを含めた動物の知覚システムの特徴を考察するためには、複数の動物種間で複数の錯視図形をテストし、種間の類似点だけでなく相違点も明らかにする必要がある。 我々は、ヒトとは系統的発生的に離れた種である2種の鳥類(ハト、ニワトリ)において、長さの錯視(順・逆ミュラー・リヤー錯視)、大きさの錯視(エビングハウス・ティチェナー錯視)、角度錯視(ツェルナー錯視)が、どのように生じているかを、種間で同一の実験手続きを用いることによって比較した。結果、いずれの錯視図形に対しても、同化現象は鳥類でも生じるが、対比現象は鳥類では生じない可能性が示唆された。視覚情報処理特性を比較した先行研究から、ヒトにおける全体志向的(global-oriented)、ハトにおける局所志向的な(local-oriented)処理傾向が示唆されており、こうした違いが、対比現象におけるヒトと鳥類との種差に関係しているのかもしれない。 |
||
| 第20回 | 2010/3/17 (水) |
大塚 一路 (東京大学 先端科学技術研究センター) |
| 人の集団に関する新たな評価方法の考察 ~ ファイナンス理論を用いたサービスレベルの評価方法 ~ |
||
|
本研究はファイナンス理論の枠組みを用いて「人混みに値段をつける」ことを目標としている。そこで我々は混雑における人の満足度が顧客一人あたりに与えられるパーソナルスペースと同等であると仮定してサービス価値の変化を正味現在価値(NPV)
法と呼ばれる資産価値評価理論によって評価した。また、新たな試みとして、サービスの価値 (顧客の効用)
が待ち時間の増加に伴って割引かれるという概念を導入し、空港の入国管理場で測定したデータに対する実証分析も行った。解析を進めるに先立って、我々は行動経済学や信頼性工学の考え方を応用して人の効用に関する割引率をアンケートを通じて見積もっている。実証分析の結果から、今回導入した指標は待ち時間の増加やスペースの減少と連動して効用が小さくなる指標となっており我々の直感と合うことが確認できた。これまで実務で用いられてきた
レベル オブ サービス(LOS) という指標では時間に関する満足度の変化は考慮されていなかったのでそういった意味でも今回提案した指標は従来の概念が改善されたものとなっている。 ※千葉大学 COEスタートアッププログラム講演会 / 第20回千葉視覚研究会 (プログラム・要旨PDF) |
||
| 第20回 | 2010/3/17 (水) |
下村 義弘 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻) |
| 『カラダの百科事典』に見るヒトの科学的考察 | ||
|
日本生理人類学会編の最新書籍『カラダの百科事典』では、全身的協関や生理的多型性などの独自の視点から、現代を生きているヒトについて様々な考察が描出されています。本講演では、その中でも特に視覚を始めとするヒトの感覚に絞って、いくつかのトピックを紹介し、人間全体という広い視野でどのように科学的考察を進めるべきかについて、示唆を共有したいと思います。 ※千葉大学 COEスタートアッププログラム講演会 / 第20回千葉視覚研究会 (プログラム・要旨PDF) |
||
| 第19回 | 2010/2/10 (水) |
平山 順 (東京医科歯科大学 難治疾患研究所) |
| 概日リズムの光入力シグナルとDNA損傷応答の類似性 | ||
|
概日リズムはホルモン分泌等の生理現象の周期を、主に光といった刺激を利用して外環境に適応させ維持する機構である。このリズムは全身の個々の細胞に存在する転写/翻訳に依存したフィードバックループ(分子時計)により制御されている。この分子時計はCLOCK,
BMAL1, 及びCRYの3つの因子(時計蛋白質)により構成される約24時間の周期性をもつフィードバックループである。この分子時計はゼブラフィシュから哺乳動物まで脊椎動物で広く保存されている。 概日リズムの重要な特性の一つは、外部からの光刺激を利用して、自身のリズムの周期を外環境に同調させることである。我々は、概日リズムの光同調過程を細胞レベルで解析するために、光応答性のゼブラフィシュ胚由来の培養細胞を実験モデルとして樹立した。この系を用いて、分子時計の光同調がMAPKシグナル経路の活性化を介したCRYの光誘導によることを見出した。 次に、「光照射により個体がDNA損傷に対して耐性を獲得する」現象であるPhotoreactivationに注目した。特に、ゼブラフィシュにおいて、DNA損傷修復蛋白質である光回復酵素(64PHR)の光誘導及び誘導された64PHRによるDNA損傷修復がPhotoreactivationの重要な過程であることを見出した。 今回、概日リズムの光同調とPhotoreactivationが共通のシグナル経路を介して制御されることを明らかにしたので報告する。 |
||
| 第18回 | 2009/12/9 (水) |
阿部 悟 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程) |
| 視野闘争の検討を通じた異眼間情報統合処理の解明 | ||
|
左右眼からの視覚情報はどのように統合されるのか?私はこうした両眼間での情報統合メカニズムの解明を、視野闘争と呼ばれる現象の検討から試みている。視野闘争とは、左右眼に大きく異なる刺激像を提示した場合に生じる一種の知覚的葛藤状態であり、その際には、各眼に提示された刺激像が交互に入れ替わったり、各眼の刺激像が部分的に入り混じって知覚されたりする。視野闘争時の知覚は、一方の刺激像を意識から完全に取り除くという優勢/抑制の決定によって、両眼間での競合が解決されることを示している。今回の発表では、そうした解決の基礎にある処理過程について検討した研究を紹介する。 (1) 先行刺激による闘争刺激の見えの変調現象 視野闘争時の見えは不規則に変動するが、特定の刺激を先行提示することで、その見えを変調させることができる。私たちの研究では、こうした変調効果の生じ方は時間条件等に応じて変わり、提示眼に基づく場合(先行刺激と同側眼の刺激が抑制)と、刺激属性に基づく場合(先行刺激と同属性の刺激が抑制)とがあることを明らかとした。この結果は、優勢/抑制の決定には、提示眼に基づく処理過程と刺激属性に基づく処理過程の両方が関与することを示唆している。 (2) 視覚属性間の相互作用 色縞のような複数の視覚属性を組み合わせた刺激が競合する場合には、色縞という1つのイメージ同士が競合しているのか、もしくはそれぞれの属性ごとに競合しているのか?この問題を明らかにするため、刺激属性に基づく変調効果の特性を利用し、色縞刺激を用いた変調効果の検討を行った。その結果、個々の属性ごとに競合の解決がなされていることが示唆された。 (3) 色と方位の知覚的誤結合 色と方位の統合様式についてさらなる検討を行うため、等輝度の色縞刺激を用いて変調効果の検討を行った。その結果、一方の色縞が知覚される優勢/抑制の決定に加え、色と方位の組み合わせが左右眼に提示した色縞のいずれとも一致しない誤結合の知覚が頻繁に報告された。またこの際、優勢/抑制の決定と誤結合の発生に対して先行刺激の影響は異なっていた。以上の結果は、両眼競合の解決の際に働く優勢/抑制の決定過程と、優勢となった刺激の見えを決定する過程が異なることを示唆している。 こうした研究結果から、競合の解決における視覚属性間の相互作用や、優勢/抑制の決定過程と見えを決定する過程の違いなどについて考察する。 |
||
| 第17回 | 2009/11/18 (水) |
富永 昌治 (千葉大学 大学院 融合科学研究科 情報科学専攻) |
| 絵画の質感を追求するディジタルアーカイビングについて | ||
|
美術絵画(油絵)のディジタルアーカイブへの一つのアプローチを述べる.ディジタルアーカイブは貴重な美術絵画を映像の形態で記録・保存・再生することであるが,ここでは,絵画を単にその姿を写真として保存するのではなくて,絵画表面に特有の質感を任意の視環境で再現する方法を展開する.この過程は画像取得,画像解析,画像レンダリングの3つの段階からなる.マルチバンドイメージングシステムで,絵画表面の画像を複数枚獲得し,絵画表面の性質を表わす各種パラメータを推定する.推定したすべての性質を用いて,任意の環境における美術絵画の三次元画像を生成する. |
||
| 第16回 | 2009/10/28 (水) |
櫻井 建成 (千葉大学 大学院 理学研究科 基盤理学専攻物理学コース) |
| 非線形振動子とそれを用いた画像処理 | ||
|
私たちの目にふれる現象の多くは時間変化し、空間的“かたち”を作り出しています。心臓の鼓動など、リズムを刻むように周期的に変化する現象もあります。私たちは、非線形な“リズム“の発生とそれを基にした“かたち(パターン)“の形成に興味を持ち研究を行っています。本発表の前半では、非線形システムにおけるパターン形成・自己組織化の学術分野の紹介を行い、後半では、
我々の提案してきた、非線形モデル方程式を用いた画像処理手法を紹介します。我々の手法では、入力画像に含まれるノイズを除去するとともに確率共鳴を用いた低コントラスト画像からの輪郭抽出も可能です。これらの手法と視覚モデルとの接点などをご教授いただければ幸いです。 |
||
| 第15回 | 2009/9/4 (金) |
桐谷 佳惠 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻) |
| 電子辞書画面デザインと語の関連性の可視化 | ||
|
デザインを学ぶ学生には、研究とデザイン提案の結びつきが理解できずに悩む者が少なからずいる。デザイン提案の核となる過程の一つに、コンセプト生成がある。今回は、このコンセプト生成に認知心理学的知見を応用し、デザイン提案を行った研究事例を紹介する。既存の電子辞書の問題点とされる一覧性と学習効果に対して、WordNetを利用し、関連語を可視化して提示する方法を提案した。既存の電子辞書と学習効果を比較したところ、提案物で英単語学習を行った場合は、1週間後の語彙テストの成績が有意に高かった。問題解決型の提案を行うデザイン研究者にとって、本研究は心理学的知見の応用の仕方を示す好例といえる。 |
||
| 第14回 | 2009/7/9 (木) |
勝浦 哲夫 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻) |
| 光環境とヒト ー味覚,時間感覚,生理機能に及ぼす光の影響 | ||
|
味覚閾値が照度、色温度によって変わるのだろうか?、光色によって時間感覚は変わるのだろうか?、昼間の単波長光はヒトの生理機能にどのような影響を与えるのだろうか?こうした光のヒトに対する影響について、最近、私たちの研究室で行った研究を紹介する。 |
||
| 第13回 | 2009/6/18 (木) |
吉岡 陽介 (千葉大学 大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻) |
| 歩行時の空間把握と中心視および周辺視 | ||
|
中心視と周辺視、この2つは互いに異なる役割を担いつつ、かつ互いに相補的に働きあうことで、日常生活における多様な情報獲得活動を支えている。 これまで我々は、制限視野法を応用した新しい実験手法を開発し、それによって、特に歩行時における空間把握と、中心視および周辺視の関係を解明しようと試みてきた。今回はそうした試みのこれまでの成果を報告したい。 人間が環境中を歩行するとき、ダイナミックな環境情報の流動が視野の中で生じ、その変化に応じた積極的な情報獲得が中心視と周辺視を通じて展開されている。こうした動的な空間把握に対する中心視・周辺視の役割を探ることで、歩行空間の計画や設計に直接援用できるような有益な知見を導き出すことができると考えている。 |
||
| 第12回 | 2009/5/21 (木) |
吉川 拓伸 (千葉大学 大学院 融合科学研究科・博士後期課程/資生堂) |
| 肌色の白さ知覚について ―色相および彩度が肌色の白さ知覚に与える影響― |
||
|
肌色の白さを定量的に評価するために、色彩計による肌色測定と、そこから得られる明度等が指標として使われている。しかし、数多くの肌色を測定した経験から、必ずしも測定された明度と白さ知覚が一致しないことがわかってきた。本研究では、この測定された明度と白さ知覚とのズレを定量的に調査し、より感覚にあった肌色の白さ指標や肌色表示空間の開発につなげることを目的としている。 まず、肌色の白さ知覚量は明度だけで決まるわけではなく色相と彩度が影響すると仮定し、顔画像の色相と彩度を独立に変化させた刺激を作成し、白さ評価を行った。実験は、色相または彩度のみを変化させた顔画像と同じ白さ感になるように基準顔画像の明度を調整し、マッチング後の基準顔画像の明度を知覚された白さとした。同様の実験を顔画像と同じ平均色情報を持つパッチ画像(正方形)でも行った。 その結果、顔画像では、色相が赤みになるほど、彩度が下がるほど同じ明度でも知覚される白さが上昇し、その程度は色相で最大L*=2、彩度で最大L*=4であった。一方パッチ画像では色相の効果は見られず、彩度の効果は確認できたが、顔画像より小さかった。 本講演では、詳細なデータと得られた結果の化粧品への応用についても述べる。またこのような現象が起こる原因として、いくつか考えられるが結論は出ておらず、参加者とのディスカッションができればと思っている。 |
||
| 第11回 | 2009/4/16 (木) |
三分一 史和 (千葉大学 大学院 工学研究科 メディカルシステムコース) |
| 脳信号データの時空間解析 | ||
|
脳活動の時間的遷移を計測する方法として脳波(EEG)や機能的磁気共鳴画像法(fMRI)などがある。これらのデータは電極や計測voxelなどの空間座標情報に時系列が対応している時空間データであり、さらに周波数変換を施すと空間軸、時間軸、周波数軸上に再構築することができる。データ解析の代表的な方法は時間軸上では自己回帰モデル、時間-周波数軸上ではWavelet解析、空間-時間-周波数軸を同時に取り扱うことができるParallel
Factor Analysisなどがある。 本講演では、自励脳波、てんかん大脳皮質脳波、脳波とfMRIの同時計測データなどの例を基に、脳信号データ解析の概要を解説する。 |
||
| 第10回 | 2009/3/5 (木) |
青木 直和 (千葉大学 大学院 融合科学研究科 情報科学専攻) |
| ノイズ付加による画質向上効果 | ||
|
従来、画像のノイズ(粒状)は画質を低下させるため、できる限り除去しようとしてきた。銀塩写真からデジタル写真となって、ノイズ除去等の画像処理は比較的容易となったが、この画像処理や狭いダイナミックレンジ等のため、画質や質感表現の低下がみられるようになった。 これらの解決法として写真家は画像にノイズを加えることを行っている。こうしたノイズ付加により、みかけの階調やシャープネスが改善され、画質の向上効果がみられる。これらを知覚するかは人によって異なることがある。研究室で行ってきたノイズ付加に関する研究について、画質の改善や画像の好ましさ、および作画への応用などを述べる。 また、等輝度刺激の研究や絵画の色・レタッチを適用した写真作画等を紹介する。 |
||
| 第9回 | 2009/2/12 (木) |
溝上 陽子 (千葉大学 大学院 融合科学研究科 情報科学専攻) |
| 環境の色分布に影響される色知覚 | ||
|
私たちは、照明や場所、季節による変化など、視環境が大きく変化するにも関わらず、安定した物の見えを保つことができる。これは視覚メカニズムが環境に適応する機能を持っているからである。物や色の見えと周囲の環境との相互関係は、空間認識や順応メカニズムと密接に関連していると考えられる。その観点からこれまで行ってきた、室内模型や実空間・自然画像を用いた研究を紹介する。また、視環境の彩度分布が色知覚に与える影響について、最近取り組んでいる以下の研究について紹介する。 視環境の色構成が物体の色知覚へ与える影響について、例えば色順応や色の恒常性など色相方向の変化への順応はよく知られている。一方、高彩度の色と低彩度の色に囲まれているときでは彩度が異なってみえるという色域効果や、彩度方向への順応についてはあまり注目されておらず、実環境でこの効果を調べた研究は見当たらない。そこで、高彩度、低彩度の色分布をもつ室内環境の違いが彩度知覚へ与える影響を検討した。実験には2つの室内模型を用い、一方は無彩色の壁と家具、他方は有彩色の家具で構成した。各室に置かれたテスト刺激の色評価を、室内の高彩度物体の量・配置の条件を変えて行った。その結果、テスト刺激の彩度の見えの差は非常に小さいものであったが、視野の中に高彩度色の占める割合が大きい場合の方が彩度の見えが低下する傾向がみられた。室内空間においても、環境の彩度分布により物体の彩度知覚が変化することが示唆された。ただし、室内の彩度分布が物の見えに与える影響は小さいと考えられる。 |
||
| 第8回 | 2008/12/11 (木) |
木村 英司 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| 瞳孔反応を用いた視覚研究 | ||
|
今回の発表では、瞳孔反応の基本的な特性や瞳孔反応に寄与する視覚過程について簡単に紹介した後に、現在進行中の瞳孔反応を用いた両眼間相互作用の研究について紹介する。 (1) 瞳孔反応の諸特性と瞳孔反応に寄与する視覚経路 ヒトの瞳孔が光の輝度変化に対して応答することはよく知られているが、それだけではなく、色、空間パターン、運動など、様々な視覚属性の変化に対しても瞳孔は応答する。こうした瞳孔反応は異なる視覚経路の寄与を受けていることが明らかとなっており、さらに、瞳孔反応が視知覚反応と類似した特性を示すことも報告され、両反応を媒介する視覚過程が、少なくとも部分的には、類似あるいは共通していることが示唆されている。こうした知見から、不随意的生理反応である瞳孔反応は、視覚研究における他覚的・非侵襲的指標として活用できると考えられる。 (2) 瞳孔反応を他覚的指標とした両眼間相互作用の検討 2a) 異眼間抑制による瞳孔反応の変化 高コントラストの縞刺激を一方の眼に提示すると、他方の眼に対して抑制効果が生じ、刺激の検出閾が上昇する。こうした異眼間抑制事態における瞳孔反応を検討したところ、瞳孔反応においても抑制効果が認められ、瞳孔反応の振幅が減少することが確認できた。こうした抑制効果は、検出閾と瞳孔反応とで類似しており、輝度刺激と色刺激に対してほぼ同程度の強さで生じた。さらに瞳孔反応の結果から、抑制効果が皮質の視覚過程だけでなく皮質下にも及ぶとことが示唆された。 2b) 見えの変化にともなう瞳孔反応の変動 視野闘争を利用して同一の刺激系列により異なる見えの変化を生じさせ、瞳孔反応が刺激の物理的な変化と見えの変化のどちらに対応して変化するかを検討した。両眼の対応部の一方に白い円刺激、他方に黒い円刺激を提示すると視野闘争が生じ、単眼に提示した白刺激と黒刺激が時間的に入れ替わって知覚される。ここで、黒刺激が優勢になっている際に両眼に白刺激を提示すると、見えの変化は黒→白となる。これに対して白刺激が優勢になっている際に両眼に白刺激を提示すると、先の場合と刺激の物理的な変化は同一であるにもかかわらず、見えの変化は白→白となる。こうした2つの条件下で瞳孔反応を測定したところ、瞳孔反応の変化は、物理的な刺激変化よりも見えの変化に強く対応する形で変化した。 こうした研究結果から、視覚研究における客観的指標としての有用性や限界について考察する。 |
||
| 第7回 | 2008/11/6 (木) |
大沼 一彦 (千葉大学 大学院 工学研究科 人工システム科学専攻) |
| 眼内レンズと色収差、球面収差 | ||
|
眼内レンズは、水晶体が混濁し、散乱光が増えて見にくくなった時に、水晶体を摘出して、挿入されるものです。近年は、角膜の持つ球面収差を打ち消して、網膜上の光学像を良くする目的で、負の球面収差を持つ非球面眼内レンズが流行となりました。また、眼内レンズ挿入時に角膜を切開しますが、この切開する幅を狭くするために、レンズを薄くしようと、屈折率の高いアクリルを使うようになりました。しかし、アクリルはアッベ数が低く、色収差が大きい材料です。そこで、ここでは球面収差と色収差が光学像のコントラストや、解像して見える範囲(写真でいう被写界深度)とど のような関係を持っているかについて模型眼を用いた実験を行いました。 模型眼では人間の角膜のもつ色収差と球面収差と同じレンズを用いて、水槽にいれた眼内レンズを通過後の像をCCDで受ける構造となっています。また、波長毎の像をえるため、干渉フィルターを用いています。 結論からいいますと、色収差は解像して見える範囲を少しだけ広げているようです。しかし、コントラストを下げているようです。 さて、実験をしていて、ひとつの疑問が出てきました。これらの像からどういう処理により色収差のない像を人間の視覚系は作っているのだろうか? このメカニズムについて関心があるかたにご指導いただけましたら幸いです。 |
||
| 第6回 | 2008/10/9 (木) |
小山 慎一 (千葉大学 大学院 工学研究科 デザイン科学専攻) |
| 幻肢とラバーハンドイリュージョンを通じて触知覚メカニズムを考える | ||
|
幻肢とラバーハンドイリュージョンは触れられていない、もしくは存在すらしない腕から触知覚を感じるという奇妙な現象として知られている。小山ら(2007,
2008)は、鏡を用いた幻肢痛緩和法を繰り返した患者において失われた腕のボディイメージが腕の付け根から手先に向かって回復したことを報告した。一方、ラバーハンドイリュージョンについては、視覚刺激の位置と触知覚を感じた身体部位との関係について詳細に検討し、1点のレーザーライトが手の異なる2点で同時に触知覚を生み出す場合があることを報告した(本間,小山,長田
2007)。研究会ではこれらの研究を紹介し、身体と感覚の結びつきについて考察したい。 |
||
| 第5回 | 2008/9/3 (水) |
高橋 良香 (千葉大学 工学部 デザイン工学科 人間生活工学研究室・博士後期課程) |
| 生体リズムとその光受容システム | ||
|
光は網膜にある桿体、錐体で受容され、色や明るさなどが知覚されている。しかし、光には生体リズムの調節やビタミンDの合成に代表されるような生体機能に影響を与える働きがある。今回は、生体リズムとその光受容システムについての概論(1)と私のやっている研究(2)(3)について紹介する。 (1)生体リズムとその光受容システム (2)瞳孔収縮と新規光受容器の関わり (3)メラトニン分泌抑制の推定モデル 最初に、生体リズムとその光受容システムについて、これまで行われた研究の概論を紹介する。光と生体リズムの関係に注目した研究の黎明期には、光はヒトの生体リズムに影響を及ぼさないと言われていた。しかし、1980年にA.J.Lewyらが2500 lxの白熱灯を用いた夜間の光曝露によってヒトのメラトニン分泌が有意に抑制されることを報告してから、光がヒトの生体リズムに影響を与えることが広く知られるようになった。1980年以後、ヒトを対象とした光と生体リズムの関係に関する研究が行われるようになり、その波長特性や視機能の状態および眼球の有無の影響が調べられている。2002年にはラットの網膜で桿体でも錐体でもない新規光受容器が発見され、これまで説明がつかなかった様々な現象を説明することができる糸口ができた。この新規光受容器はヒトの網膜にも存在していることが確認されている。 新規光受容器の神経出力が視蓋前域オリーブ核と視交叉上核に投射していることから、この光受容器が瞳孔収縮と生体リズムに作用していることが報告されている。ノックアウトマウスを使った研究から、新規光受容器が高放射量のときの瞳孔収縮に作用している事が示唆されている。そこで、ヒトを対象に単波長光を用いて瞳孔収縮の分光感度を調べたところ、高放射量の時の瞳孔収縮が新規光受容器によって調節されていることを示す実験結果が得られた。 メラトニン分泌の異常は冬季の間だけ、うつ病と似た症状になる季節性感情障害や交代勤務で働くヒトに乳がんや前立腺がんのリスクが高いことと関係があると言われている。そのため、光の生理面への影響を考慮した照明設計をする際、メラトニン分泌への影響を考慮する必要がある。ここでは、夜間の光曝露によるメラトニン分泌抑制率を推定するため、メラトニン分泌抑制の分光感度を使った照度と瞳孔面積の積によってメラトニン分泌抑制率が求められるかを検討した。 |
||
| 第4回 | 2008/7/30 (水) |
牛谷 智一 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| 視覚的体制化の比較認知科学 | ||
| 古くは生物学者 Uexkuell (1934)
が指摘したように、動物は、各々その環境に適応した知覚世界を持っていると考えるのは不自然ではない。しかし、それから70年以上経った現在も、動物の視知覚の適応に関しては十分にまだわかっていない。視覚情報処理過程の生物多様性を理解することで、同じ30億年の自然淘汰の産物であるヒトの視覚についての理解も深まるかもしれない。視覚的体制化に関する発表者の種間比較研究を、これまでの成果
(1 - 2)に加え、現在進行中のプロジェクト (3 - 4) を交えつつ紹介する (千葉大学の実森正子氏、京都大学の友永雅己氏との共同研究を含む)。 (1) 運動の知覚的体制化 複数の光点が暗闇の中で近接して運動するとき、それらの運動は統合して知覚される。ターゲット光点の運動方向の弁別をハトに訓練したのち、同期して動く別の物体を呈示しテストした。ハトの反応は、運動を統合して知覚していることを示唆するものであった。 (2) アモーダル補完 物体の一部がほかの物体に隠されても、我々は見えている部分から推測して隠れている部分を知覚的に補完する。ハトもこのように隠れた図形を補完するか調べた。いくつかのテストの結果は、最近の複雑な運動刺激を用いた実験も含め、いずれもハトの補完に否定的な結果であった。アモーダル補完の進化について議論する。 (3) 類同と近接の法則による体制化 2種類の色の円を格子状に並べるとき、縦の間隔を横の間隔よりも短くすると、近接の要因から縦縞模様に見える。縦横の間隔が等しい場合でも、縦を1列交替で同じ色で揃えると、類同の要因から縦縞模様に見える(縦に近接しているように知覚される)。このような類同の要因による体制化をハトが知覚するか調べる現在進行中の研究では、肯定的な結果が示されつつある。 (4) 注意レベルでの視覚刺激の体制化 視覚的注意には、注意の中心からの距離の関数で決まるような空間ベースの注意のほかに、物体のような「まとまり」を単位に賦活するような注意過程(オブジェクトベースの注意)も知られている。チンパンジーとハトの視覚的注意にもそのような機能があるか調べた。また、このような注意過程を調べる枠組みを利用して調べた視覚的体制化の研究を報告する。 |
||
| 第3回 | 2008/6/18 (水) |
外池 光雄 (千葉大学 大学院 工学研究科 メディカルシステムコース) |
| 視覚の脳内情報処理に関する非侵襲的計測 | ||
|
視覚系は、人間の感覚系の中では最も研究が進んでいる分野であるが、脳内における視覚情報処理が如何に行われているかについては解明されていないことも数多く存在している。その一つに、視覚情報で得られた物体の認知が実際に脳のどのような部位で、どのような経過を辿って処理されているかとなると、必ずしも明確にはなっていない、などがある。このように人間の現実の意識状態の脳内で行われている処理を計測・解析するには、近年急速な進歩を遂げている非侵襲的な計測を行う手法とその解析が不可欠である。 そこで、我々は、現在の最先端の計測技術を駆使して人間の脳内における感覚情報処理、特にマルチモーダルな複数感覚による感覚情報の統合的な情報処理機構の解明を目的としている。 本報告では、まず最初にそれぞれの非侵襲計測法の特徴を述べ、これらの手法の長所を組み合わせた研究の紹介と、方法論開発の試みを述べる。 次に、具体的に視覚系では現在実施している、色調の脳内情処理に関する脳磁図(MEG)計測や、fMRI計測実験の結果について紹介する。また、最近開始した人の顔画像刺激に関する脳内の知覚と認知に関する研究の現状について述べるとともに、記憶課題を用いたワーキングメモリの実験の現状などを報告する。 また、これまで行ってきた研究の中から、複数感覚同時刺激による注意の分割に関する研究や、味と匂いの感覚刺激に対して共通に応答する脳内部位の研究の実例などの紹介も行う。 最後に、筆者らが現在、研究目標としている前頭眼窩野の連合野部位における脳内の感覚統合に対する情報処理の仮説モデルについて述べる。 |
||
| 第2回 | 2008/5/21 (水) |
宗方 淳 (千葉大学 工学部 建築学科) |
| 建築空間の見せ方、見方 | ||
|
建築空間はその設計段階から完成後の様々な段階において視覚的な印象の評価が行われる。例えば、設計者による意匠の検討、地域住民のための説明会、法規制のための研究など様々な場において、映像や実空間を対象として建築空間を見る・見せるという行為が発生する。 発表者は「映像の見せ方が建築空間評価に及ぼす影響」や「(実際の)建築空間の視覚的な印象がどのような要因によって決まるか」といった関心事のもと様々な研究に携わってきた。今回の研究会においては主として次の二点について発表する。 (1)映像の提示方法が建築空間印象に及ぼす影響 スクリーン上に映像を投影して提示する際、映像の撮影画角とスクリーンに対する観察位置からの画角は必ずしも一致しておらず、この差異は映像の空間印象に違いをもたらすことが考えられる。そこで、映像の提示画角設定と映像の大きさそのものを要因とした映像印象評価実験を行い、主として活動性に関する印象が映像の提示画角設定により異なる結果を得た。また、注視点分布の検討も別途行い、提示画角により分布に違いが生じる結果も得た。 (2)建築物から受ける圧迫感に関する検討 我国の建築関連法規においては建物の大きさに関する規制は幾つかあるものの、圧迫感という観点からの定量的な規制には未だ至っていない。圧迫感に関するこれまでの知見としては、映像シミュレーションによる実験 を中心として行われ、対象とする建築の立体角投射率が最も説明力が高いとされている。発表者は幾つかの実験を通して、無意識的な現場の記憶が意識的な評価実験との相関が高いことや、圧迫感評価において立体角投射率だけではなく対象建物の縦横比を織り込むことで説明力が上がることなどの結果を得ている。 |
||
| 第1回 | 2008/4/23 (水) |
一川 誠 (千葉大学 文学部 行動科学科) |
| 能動的観察によるフラッシュラグ効果の低減 | ||
| 定速で運動する刺激と並んだ位置に一過性の刺激(フラッシュ)を提示した場合、2つの刺激の間に実際にはないズレが知覚される。これはフラッシュラグ効果と呼ばれる錯視である。本研究では、観察者の能動的な刺激操作が視覚に及ぼす影響をフラッシュラグ効果を題材として検討する。一連の実験では、いくつかの条件において観察者がコンピューターマウス等のデバイスを使って刺激運動を能動的にコントロールした条件で得られるフラッシュラグ効果と、刺激が自動的に運動した条件で得られるフラッシュラグ効果とを比較した。マウスを用いた条件では、マウスと刺激の運動方向とが一致している場合、観察者がマウスを用いて運動刺激をコントロールする条件、および、刺激が実際には自動的に刺激をコントロールしていても観察者が自分で刺激を動かしていると感じられる条件では、フラッシュラグ効果が減少することが見出された。他方、マウスと刺激の運動方向が一致していない条件では、このようなフラッシュラグ効果の現象は認められなかった。これらの結果は、観察者の能動的運動が視覚情報処理を促進させうること、ただし、そのためには能動的運動と刺激運動との方向的一致が重要であることを示唆している。実験結果から、能動的観察による視覚における運動処理への寄与について考察する。 |
関連講演会
| 2017/3/17 (金) |
千葉大学 大学院融合科学研究科 メタ適応知性システムの構築プロジェクト |
| Meta-Adaptive Intelligent System (MAIS) -Project Symposium | |
| 日時:2017年3月17日(金) 13:00〜16:40 場所:千葉大学西千葉キャンパス 工学系総合研究棟2 2F コンファレンスルーム 13:00-13:20 Introduction of MAIS-Project: Prof. Yoshitsugu Manabe (Chiba University) 13:20-13:40 Pedestrian Navigation Application: Prof. Makoto Ichikawa (Chiba University) 13:40-14:00 Environmental Information Collection System with IoT: Associate Prof. Nobuyoshi Komuro (Chiba University) 14:10-15:10 Lab-forming Field and Field-forming Lab: Dr. Takeshi Kurata (AIST) 15:20-16:35 Visual Perception and Adaptation in Natural and Unnatural Environments: Prof. Michael A. Webster (University of Nevada, Reno) 16:35 Closing ---------------------------------------------------- "Lab-forming Field and Field-forming Lab" Dr. Takeshi Kurata (AIST) I present the concept of Lab-Forming Fields (LFF) and Field-Forming Labs (FFL). LFF is to transform real service fields into lab-like places for bringing research methodologies in laboratories to real fields with IoT. FFL is to transform laboratories into real-field-like places for getting subjects’ behavior and experimental results closer and closer to the ones which are supposed to be obtained in the real service fields with VR. Next, I introduce indoor positioning technologies such as PDR (Pedestrian Dead Reckoning) as a key technology for human behavior sensing. Then I conclude this talk by briefly reporting on case studies of service kaizen in a restaurant and a warehouse respectively. ---------------------------------------------------- “Visual perception and adaptation in natural and unnatural environments” Prof. Michael A. Webster (University of Nevada, Reno) Processes of adaptation continuously adjust visual sensitivity to match the characteristics of the current environment. These adjustments affect most aspects of perception, inducing large differences in visual experience when the same observer is exposed to different worlds, while similar experiences when different observers are exposed to the same world. I will explore the consequences of these adaptation effects for understanding how perception and visual performance can vary within both the natural environments we evolved in, and the increasingly artificial and specialized technological environments to which humans are currently exposed. To the extent that we understand the statistics of the environment and how vision adapts to them, the perceptual consequences of adaptation can be modeled and potentially optimized by adapting images to match the observer. ---------------------------------------------------- ※ 詳細はこちら |
|
| 2014/6/10 (火) |
土谷尚嗣 (Monash University) |
| The integrated information theory of consciousness applied to the empirical electrophysiological recording data sets | |
| 土谷先生講演会 日時:2014年6月10日(火) 13:00-14:00 場所:千葉大学 自然科学系総合研究棟2号館2階 マルチメディア講義室 Title: The integrated information theory of consciousness applied to the empirical electrophysiological recording data sets Abstract: Integrated information theory of consciousness is one of the most promising theories currently available that can explain enigmatic features of consciousness (Oizumi et al 2014 PLoS Comp, Balduzzi & Tononi 2008 PLoS Comp). Despite its theoretical appeals, it has been less influential due to the fact that it is impossible to compute the exact amount of integrated information in real biological systems due to a huge amount of computation involved. Recently, we developed an analytical approximation of the integrated information, which can be applied to the real neuronal data. By applying our measure to the real neuronal data, we have been testing the prediction of the theory in terms of the level and contents of consciousness; that the integrated information should be lower when people, monkey, or even flies, lose consciousness due to anesthesia, sleep or epilepsy; that the structural relationship of integrated information should mirror the contents of consciousness. Though it is still preliminary, I will present several recent results from this project. |
|
| 2010/4/16 (金) |
M. Ronnier Luo (University of Leeds) |
| Holy Grail of Colour Appearance Research | |
| Prof. M. Ronnier Luo講演会 日時:2010年4月16日(金) 10:30-12:00 場所:千葉大学 自然科学系総合研究棟2号館2階 マルチメディア講義室 概要: M. Ronnier Luo, University of Leeds (UK) A general review of Robert Hunt’s contribution to color science since his initial work in 1950 will be given, focusing on the topic with which he was most involved: color appearance. Starting with his initial research on adaptation ― he investigated changes in color appearance due to different illuminants and luminances of adaption fields ― we will then discuss his work defining terms for visual correlates such as hue and brightness and proposed methods for formulating them. After looking at Hunt’s work establishing the framework of color appearance models, this talk will explain his contributions to the generation of large psychophysical data sets for the testing of various models, particularly CIECAM97s and CIECAM02. ----------- ※ この講演会は大学院GP・ナノイメージングセミナーの一環として開催されました。千葉視覚研究会共催。 |
|
| 2009/7/29 (水) |
James A. Ferwerda (Munsell Color Science Laboratory, Chester F. Carlson Center for Imaging Science, Rochester Institute of Technology) |
| Envisioning the material world | |
| James A. Ferwerda先生講演会 講演者:James A. Ferwerda (Munsell Color Science Laboratory, Chester F. Carlson Center for Imaging Science, Rochester Institute of Technology) 日時:平成21年7月29日(水)13:00~ 場所:工学部5号棟 104講義室 タイトル:Envisioning the material world Efforts to understand human vision have largely focused on our abilities to perceive the geometric properties of objec such as shapes, sizes, and distances, and have neglected the perception of materials. However correctly perceiving materials is at least as important as perceiving objects, and human vision allows us to tell if objects are hard or soft, smooth or rough, clean or dirty, fresh or spoiled, and dead or alive. Understanding the perception of material properties is therefore of critical importance in many fields. In this talk I will first show how we have been using image synthesis techniques to develop psychophysical models of material perception that can relate the physical properties of materials to their visual appearances. I will then describe how we have been taking advantage of the limits of material perception to develop new techniques for efficiently rendering complex scenes. Finally I will discuss some recent efforts to develop advanced display systems that allow more realistic visualization of complex objects and materials, and allow hands-on interaction with virtual surfaces. ----------- ※ この講演会は大学院GP・ナノイメージングセミナーの一環として開催されました。 |
| 歴史 |
千葉視覚研究会は、10年ほど前まで行われていたそうです。その後活動が途絶えていたものを、2008年4月に復活させた形になります。したがって、現在の千葉視覚研究会は、正確には(「新」もしくは「復活版」)千葉視覚研究会となります。
| 問い合せ先 |
溝上陽子 (千葉大学大学院工学研究院)
![]()
Last updated : 2019/2/17
(C) 2008-2019 Chiba Vision Meeting. All Rights Reserved.